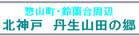
Top Page
北神戸 丹生山田の祭 (*21)(*26)(*33)(*39)
山田の伝統行事・祭礼は丹生山田郷全体で行うものと山田13か村(現在は字)の各々の村で行うものの2階層になっている。
山田郷全体で行うものは山田の総鎮守である六條八幡神社 (一部は七社神社
(一部は七社神社 )で行われ、その年の当番となった地区(村)によって執行される
)で行われ、その年の当番となった地区(村)によって執行される
以下は、山田各地区の主として鎮守社で行われている。祭礼の呼び名や方式、祭礼日は微妙に異なるが、共通するものが多い。
 、西下の天津彦根神社、下谷上の天彦根神社
、西下の天津彦根神社、下谷上の天彦根神社 ・八坂神社
・八坂神社 ・壽福寺
・壽福寺 、中の清光寺
、中の清光寺 、東下の七社神社
、東下の七社神社 、福地の若王子神社
、福地の若王子神社 、小部の杉尾神社
、小部の杉尾神社 ・大歳神社
・大歳神社 で行われている。
で行われている。 ではワラ人形、無動寺
ではワラ人形、無動寺 (福地)のオコナイでは渦巻き型の実印。無動寺と若王子神社が共同で行うオトウ(シューシオコナイ)はかつての神仏習合の姿をとどめ日本の祭り百選にも選ばれている(*26)。無動寺の他、坂本の永徳寺
(福地)のオコナイでは渦巻き型の実印。無動寺と若王子神社が共同で行うオトウ(シューシオコナイ)はかつての神仏習合の姿をとどめ日本の祭り百選にも選ばれている(*26)。無動寺の他、坂本の永徳寺 、東下の大歳神社・七社神社、西下の最法寺
、東下の大歳神社・七社神社、西下の最法寺 毘沙門堂、衝原の大歳神社(昭和初期まで)など。
毘沙門堂、衝原の大歳神社(昭和初期まで)など。 、かつては藍那、上谷上(青年会)でも行われていた。
、かつては藍那、上谷上(青年会)でも行われていた。
以下は昭和50年代の「山田郷土史」(*21、昭和54)、「神戸の民俗芸能 兵庫・北編」(*33、昭和52)、「北神戸 歴史の道を歩く」(*26:平成14)と「北区歳時記」(*39:平成18)に紹介されている祭礼を示す。
| 開催日 | 場所(地区) | 祭礼・伝統行事 |
|---|---|---|
| 1月4日 | 大歳神社 (小河) |
お弓(*33) 毎年2人の射手が的(竹組み紙を張り、中心に鬼と書いた後塗りつぶす)に向かって1人2矢ずつ3度交代して、計12本の矢を放つ |
| 1月8日 | 清光寺 薬師堂 薬師堂(中) |
オトウ(オコナイ)(*26) |
| 1月第2日曜 | 天彦根神社(八ちやはん) (下谷上) |
マト(*33)(*39) 6人の射手が的(丸い竹組みに表に3重円を書いた半紙を、裏に鬼と書いた半紙を貼り付けたもの)に向かって1人2本ずつ3巡、計36本の矢を放つ(16日に八坂神社で、17日に壽福寺で同様の行事が行われる) |
| 1月第2月曜 成人の日 |
壽福寺 (下谷上) |
大般若経法要(*39) 大般若経を転読し参詣人の無病息災を祈願 |
| 1月16日 | 八坂神社(天王さん) (下谷上) |
マト(*33) 6人の射手が的(丸い竹組みに表に3重円を書いた半紙を、裏に鬼と書いた半紙を貼り付けたもの)に向かって1人2本ずつ3巡、計36本の矢を放つ(10日に天彦根神社で、17日に壽福寺で同様の行事が行われる) |
清光寺 (中) |
お弓(*33) 各隣保の代表5人の射手が的(1.5m四角のベニヤに張った紙に3重円を書き中心部は鬼と書いた後で塗りつぶす)に向かって1人5本ずつほどの矢を放つ |
|
| 1月17日 | 七社神社 (東下) |
引目祭(*21)(*33) お弓引ともいい、抽選で選ばれた6人の射手が20m離れた直系約1.5mの的(割竹で編み紙を張って墨で2重円を書いたもの)に向かって1人2本ずつ3巡、計36本の矢を放つ |
壽福寺 (下谷上) |
マト(*33) 6人の射手が的(丸い竹組みに表に3重円を書いた半紙を、裏に鬼と書いた半紙を貼り付けたもの)に向かって1人2本ずつ3巡、計36本の矢を放つ(10日に天彦根神社で、16日に八坂神社で同様の行事が行われる) |
|
| 1月19日 | 六條八幡神社 (中) |
厄除大祭(引目神事)(*21) お弓引とか疫神祭(えきじんさい)とも言い、悪魔を示す文字を書いた的を弓で射る。11時頃からの拝殿での祭典に続き11時半頃から境内で神事が始まる。七社神社の引目祭同様、抽選で選ばれた6人の射手が大石灯籠辺りに据えられた20m向こうの直系約1.3mの的(裏側中央に「ム」の無い鬼の字3字が書かれる)に向かって1人2本ずつ3巡、計36本の矢を放つ。矢を射る度にはぜの木で作った数取りの木を席の前の砂盛に刺す。秋の流鏑馬の当番部落が催行する。終了後、福娘による餅撒きが行われる。 お弓引とか疫神祭(えきじんさい)とも言い、悪魔を示す文字を書いた的を弓で射る。11時頃からの拝殿での祭典に続き11時半頃から境内で神事が始まる。七社神社の引目祭同様、抽選で選ばれた6人の射手が大石灯籠辺りに据えられた20m向こうの直系約1.3mの的(裏側中央に「ム」の無い鬼の字3字が書かれる)に向かって1人2本ずつ3巡、計36本の矢を放つ。矢を射る度にはぜの木で作った数取りの木を席の前の砂盛に刺す。秋の流鏑馬の当番部落が催行する。終了後、福娘による餅撒きが行われる。山田の多くの部落でも同様に1月中に引目祭が行われる。 写真(クリックでビデオ映像)は2007年の厄除大祭で、当番地区は上谷上 |
天津彦根神社 (原野) |
厄除祭(引目祭)(*39) 御神酒、山海の珍味のお供え、直会の後、弓引き神事を行う。 |
|
八坂神社 (原野) |
厄除祭(引目祭)(*39) 御神酒、山海の珍味のお供え、直会の後、弓引き神事を行う。 |
|
| 1月中旬 | 森林植物園 (下谷上) |
とんどやき(*39) 阪神・淡路大震災の鎮魂の意を込めて門松やしめ飾りを燃やして無病息災を願う左義長(とんどやき)を行う |
| 2月5日 | 若王子神社 ・無動寺  (福地) |
シューシ・オコナイ(*26)(*21) 福地の無動寺にある若王子神社で2月5日、10月5日の年2回行われる奇祭。 福地の東西いずれかの部落から選ばれたその年の神主(15歳くらい。2月5日の祭後、無動寺住職が立会い抽選で決める)が若王子神社に参詣し、お供え、祝詞、玉串奉納までは、普通の祭典だが、この後、無動寺の庫裏に場所を移しての直会(なおらい)が奇習である。 まずシューシは、正座の専任の神職と無動寺の住職、それに連なる部落の長老以下に対して裃姿の神主が下座からお頭(しゅうし)の挨拶をする。その後杯を順次大きなものに替えながらの酒宴が行われる。シューシ後のオコナイは、住職が読経する中、部落の人々が樫や椎の棒2本を先が割れるまでたたきつける。割れた先には護符を挟んで持ち帰り、1本は稲の豊作を祈願して稲苗代の水口に立て、もう1本は家の床に祭って家内安全を祈願する。 |
| 2月11日 建国記念日 |
天津彦根神社 (西下) |
お弓(*33)(*39) 毎年2人の射手が的(直径1.5mの竹組みに表に2重円を書いた半紙を、裏に鬼と書いた半紙をあてたもの)に向かって1人2矢ずつ3度交代して、計12本の矢を放つ |
| 2月16日 | 若王子神社 (福地) |
弓引き(*33) 輪番制の上番(去年の神主)・下番(今年の神主)の2人が的に向かって旧・新・旧・新の順に3本ずつ、計12本の矢を放つ |
| 2月21日 | 大歳神社 (小部) |
引目祭(関連リンク) |
杉尾神社 (小部) |
マト 3地区から2人ずつ選ばれた長男が鬼と書いた半紙をとめた木の枠で作った的に1人2本ずつ3回矢を射る。悪魔祓いの行事でビシャとも言う |
|
| 2月22日 | 稲荷神社 (小河) |
子供相撲 稲荷社の祭日に幼稚園から小学生の男子が奉納相撲をする |
| 2月上旬 | 森林植物園 (関連リンク) (下谷上) |
冬芽(とうが)観察会と七草がゆ(*39) 春を待つ冬芽(とうが)観察会の後、七草がゆを食べる |
| 3月初午 | 無動寺 (福地) |
子供相撲(*33) 3月初午の日に小学生までの幼児・児童を集めて学年ごとに相撲をとる。寒さよけにこの日まで取っておいた正月の飾り付けでトンドをする。 |
| 5月5日 | 丹生神社 (坂本) |
申祭(丹生祭)(*21)(*33) 丹生神社に併祭される日吉神社の使いとされる猿にちなんでいると思われ、かつては旧暦4月の申の日に行われていた。 丹生神社に併祭される日吉神社の使いとされる猿にちなんでいると思われ、かつては旧暦4月の申の日に行われていた。古くから奉納相撲が有名で、鎮守としている坂本、東下、西下だけでなく、山田郷内はもちろん遠く三木、志染(しじみ)、淡河(おうご)、吉川(よかわ)あたりからも力自慢の田舎力士が集まった。 今は地元小学校の生徒による子供相撲が奉納されている。 |
| 7月10日 | 八坂神社 (原野) |
夏祭り(祇園祭)(*39) 氏子の浄財と餅米を神殿に供えた後、餅撒きを行う |
| 7月第3日曜 | 天津彦根神社 (原野) |
夏祭り(*39) 氏子の浄財と餅米を神殿に供えた後、餅撒きを行う |
天彦根神社 (下谷上) |
夏祭り(*39) 当番の氏子夫婦が櫓の上から餅撒きを行う |
|
| 7月第4日曜 | 箕谷神社 (下谷上) |
夏祭り(*39) 餅撒きを行う |
| 8月24日 | 愛宕神社 (小河) |
子供相撲 愛宕社の祭日に幼稚園から小学生の男子が奉納相撲をする |
| 9月9日 | 大歳神社 (中) |
子供相撲(*33) 大歳神社の例祭の後、小学生以下の子供たちが交代で相撲をとり、居合わせた大人が行事役をする |
| 9月第3日曜 | 六條八幡神社 (中) |
神幸祭(神輿担ぎ祭)(*21) 4組に分かれた氏子の部落が輪番で神輿を担いで部落の氏神から六條八幡神社まで練り歩き、その後、昼の休憩を挟んで六條八幡神社の境内を練りまわる。 |
| 10月5日 | 若王子神社 ・無動寺  (福地) |
シューシ・オコナイ(*21) (2月5日の若王子神社のシューシ・オコナイ参照) |
| 10月第1日曜 | 箕谷神社 (下谷上) |
秋祭り(*39) 畦豆と甘酒が振舞われる |
| 10月第2日曜 | 七社神社 (東下) |
 流鏑馬神事 流鏑馬神事六條八幡神社での「駆け入り」の前の「駆け出し」の儀式。 東下の大歳神社参拝後、七社神社で祭典に続いて神社前の参道を板の的に向かって騎射した後、鳥居までの馬場を疾駆する。 午後の六條八幡神社での流鏑馬神事のために、沿道を行列が練り歩く。 |
六條八幡神社 (中) |
流鏑馬神事 馬駆け(うまかけ)とも言われ参道入り口の鳥居から本殿に向かって馬を駆けさせながら的を射る勇壮・華麗な神事。午前中の七社神社の流鏑馬に引き続いて行われる。流鏑馬が騎射であるのに対して、1月の引目神事では、歩射と言って徒歩で的を射る。 馬駆け(うまかけ)とも言われ参道入り口の鳥居から本殿に向かって馬を駆けさせながら的を射る勇壮・華麗な神事。午前中の七社神社の流鏑馬に引き続いて行われる。流鏑馬が騎射であるのに対して、1月の引目神事では、歩射と言って徒歩で的を射る。写真(クリックでビデオ映像)は2006年の流鏑馬神事で、当番地区は西下 |
|
| 10月12日 | 天津彦根神社 (原野) |
甘酒祭り(*39) 茹でさえ(枝豆)を神殿に供えた後、茹でさえと甘酒が振舞われる |
八坂神社 (原野) |
甘酒祭り(*39) 茹でさえ(枝豆)を神殿に供えた後、茹でさえと甘酒が振舞われる |
|
| 12月第1日曜 | 天津彦根神社 (原野) |
新嘗祭(*39) 株つき稲穂と新餅を神殿に供える |
八坂神社 (原野) |
新嘗祭(*39) 株つき稲穂と新餅を神殿に供える |
|
| 厳島神社 (原野) |
新嘗祭(*39) 株つき稲穂と新餅を神殿に供える。 ここには栗花落(つゆ)の井の伝説がある。 |