「 バレンタイン異聞 」 「ミロ………」 喉の奥から搾り出すような悲痛な声がとろとろと心地よくまどろんでいたミロを驚かせたのは、深夜を過ぎた頃だった。 はっとして隣りのカミュを見た瞬間に異変に気付いたのも当然だ。 たとえようもない冷気がカミュを包んでいたではないか。 仄かな灯りの中で見る白い頬にはまったく血の気がなく、胸の上に置かれた手は既に凍っているかのように見えるのだ。 「カミュっ!」 いったいどうして、隣りに寝ていてそれに気付かなかったのだろう、愕然としながら自分を責めたミロが急いで肩をつかもうとしたときだ。 「よせ………私に触れるな…………お前が凍ってしまう……」 薄く目を開け、切れ切れにやっとそれだけ言ったカミュが力なく目を閉じる。 「冗談じゃないっっ、カミュ!頼むから目を開けてくれ!」 思わぬ事態に畏怖したミロの声だけが、凍った闇を震わせた。 ほのかにゆらめきながらカミュを包んでいるのは、明らかに自らが生み出している小宇宙だ。 ………なぜ、こんなことになったんだ? ついさっきまでは、なんでもなかったのに! 外部からの小宇宙が作用したはずはない、それなら俺にわからぬはずはないのだ しかし、なぜカミュが自らの冷気で自分をここまで痛めつける? そんな理由がどこにある? 宵のうちはミロの愛にあれほどいとおしく応えてくれたカミュが、今は同じ我が手の中で冷たく動かなくなっていることにどうして納得できようか。 氷のように冷え切ったカミュの身体を抱きながら、ミロは答えのない問いをくりかえす。 カミュの言葉には耳を貸さずにその身体をかきいだいたときには本当に心臓が凍るかと思ったが、ありったけの小宇宙を振り絞り、ミロはかろうじて意識を失わずにすんだのだ。 あそこで踏みとどまらなければ、共倒れしていたに違いない。 ミロがほっとしたことには、カミュの心臓はゆっくりではあるが規則正しい鼓動を続けており、緩慢ながら自発呼吸もできている。 意識を呼び覚まそうと途切れなく呼びかける言葉にも、かすかにまぶたを震わせて反応が返ってくるのだった。 このぶんなら他からの助けを借りなくてもよさそうで、ミロは安堵の胸を撫で下ろさずにはいられない。 シャカやムウあたりならもっと的確な処置が施せるのかもしれないが、 今はどうあっても自分ひとりだけでやり遂げねばならぬ。 なんといっても、道で倒れたのとはわけが違い、この状態で人を呼べるはずがないのである。 他人に助けられたと知ったとき、カミュがどれほど傷つくか、ミロには容易に想像できた。 水と氷の魔術師とまで呼ばれるほどのカミュが創り出した冷気には、通常の方法ではとても対処できるはずもなく、黄金聖闘士のミロが最高レベルで小宇宙を燃やしても意識を回復させるのは至難の業だ。 果てしなく続くように思われる闇の中でカミュを抱きながらミロが思い出すのは、かつての宝瓶宮戦のあとのことにほかならぬ。 カミュが宝瓶宮で氷河と闘い、ともにオーロラエクスキューションを撃ち合って倒れたとき、天蠍宮に在ってそのことを瞬時に察知したミロは断腸の思いで宝瓶宮へと駆けつけ、大理石の床に冷たく打ち伏すカミュを見い出すことになったのだ。 かすかに感じられる微弱な鼓動を一縷の頼りに、カミュを抱きかかえ天蠍宮へと馳せ戻ったミロは、歯を食い縛りながら絶対零度にも等しい凍気との闘いに勝利を収め、ついにカミュをその手に取り戻したのだった。 あとから思えば、そのときすでに聖域を覆っていたアテナの小宇宙がかげながら助けてくれていたに違いないのだが。 それに黄金聖衣を身につけていたことも功を奏したのに違いない、そうでなければ絶対零度にも等しい冷たさに凍え切っていたカミュに触れた途端に、ミロの身体さえも瞬時に凍り付いていたはずではないか。 今夜のミロにはむろん聖衣の助けはないが、抱きしめているカミュの冷たさは決してあの時の絶対零度のようなものではない。 時間さえかければ、きっとカミュの意識が戻るという確信がミロにはあったのである。 朝までに………きっと朝までにはカミュは目を開けてくれる 俺は必ずカミュをこの手に取り戻してみせる! そうせずにはおくものか! それにしても、宝瓶宮戦のときとは違い、カミュは凍気を浴びもしなければ、むろん放ってもいないのだぞ! 俺に抱かれて穏やかに眠りに落ちていったはずのカミュにいったい何が起こったのだ? 今回は助かっても、また再び同じことが起こったらどうすればいいのだ? 先の見えない不安を抱いたまま、ミロはカミュをおのれの小宇宙でひたすら暖め続け、やがて夜が明けて鳥のさえずりが聞こえてきたとき、紙のように白かったカミュの頬にわずかに赤味がさしてきた。 しめたっっ! ここぞとばかりに凍えた指をさすり、冷たいうなじに唇を寄せ、これ以上はないというやさしさで硬直した身体を包み込んでやる。 氷の糸のように冷たい光を帯びていた髪はすでに元の艶やかさを取り戻しつつあり、それが、小宇宙を使い果たしてしまうのではないかと恐れるミロに勇気を与えてもくれるのだ。 間断なく耳元で語りかけるミロの声にも、まつげを震わせる回数が増えてきているのは、よい兆候だった。 「カミュ………俺のカミュ……目を開けて…………頼むから……」 幾百回となく、それこそ数え切れぬほどに繰り返しただろうその言葉を動かぬ身体に注ぎかけているミロには、もうほかのことを考える余裕もなくなっている。 やがて時刻は正午に近くなり、あまりの目覚めの遅さに不安を募らせたミロが、ついに誰かの助けを呼びに行こうかと考え始めたそのときだ、カミュが薄く目を開けた。 かすかに動く唇が、ミロにとっては黄金にも等しい言葉を紡ぎ出す。 「…ミロ………私は……」 「カミュ…俺のカミュ………」 それきり言葉をなくしたミロにかきいだかれたカミュが低く呻き、その声さえもミロには甘く響くのだ。 ほっとしたとたん涙の粒がふくれあがり、はらはらとこぼれてカミュの頬を濡らした。 「ミロ……お前の涙が…熱い……」 淡く笑ったカミュのなんと懐かしく美しく思えたことか、そのときになって、やっとミロには永遠にも等しかった夜が明けたのである。 「カミュ……どうしてこんなことになったのか、お前、わかる……?」 これ以上はない安堵感に身をひたしながらカミュを抱き締めて離さないミロが問いかける。 「ほんとにお前には心配をかけて……すまぬ……ほんとにすまなかった…」 しなやかにたおやかにカミュの手がミロをいつくしみ、その生きている証しの仕草がミロを包み込んでなんと安心させてくれることだろう。 昨夜来の冷たさの翳りもとうに失せ、想いを込めた口付けを与えるたびに、それに勝るとも劣らない熱を込めた口付けがカミュから返されてミロを喜ばせた。 「昨夜……お前に抱かれているときに、ふとあの時のことを思い出したのだ……氷河と闘ったときのことを。 それがきっかけになったのだと思う。」 「たったそれだけであんなことに? そいつはひどすぎやしないか? あやうく死ぬところだったんだぜ!」 死という言葉をつい口に出したミロは思わず首をすくめる。 何度聞いても嫌な言葉だ、ミロにもカミュにも。 「潜在意識のなせる業だとしたら、今後、何度あれに見舞われるかわかったものじゃない……まてよ? おい、まさか今までにもあんなことがあったんじゃあるまいな?」 カミュがミロの胸に顔を伏せる。 「それは………」 「隠すなよ……初めてじゃないんじゃないか?」 やさしく背中をさすりながら艶やかな髪に頬ずりしてやると、しのびやかな溜め息がミロの胸をくすぐった。 「以前、お前が任務で三日間留守にしていたとき、わけもなく寂しくなって、いろいろなことを考えた……そのとき氷河と闘ったことをひとつひとつ思い出していて………そのときに今回と同じことがあった。」 「三日間って……去年の夏のことか? そんな大事なことをなぜ黙ってた? もしかしたら死んで………いや、危なかったかもしれないんだぜ。 頼むから、そういうことを俺に隠さないでくれ!」 蒼白になったミロが腕に込めた力が強すぎたのか、カミュが小さくあえぎ身をこわばらせた。 「ミロ……ミロ………すまぬ、黙っていて。 でも、あの時は夕方で、潜在意識下で小宇宙を発現させた瞬間に自分でそれとわかり、ダメージを最小限に抑えることができたのだ。 低温状態も半日で自然に回復し、むろん後遺症も残存してはいない。 二度と、リアルに過ぎるシミュレーションはすまいと誓ったし、こんなことがあるとは思わなかったのだ。」 「でも、昨夜はそれがあった。 ………どう? 俺がいなくても、自力で回復できたと思ってる?」 深い溜め息がカミュの首筋を掠め、やさしい口付けが白い額に与えられた。 「俺は本当にお前のことが心配で心配で…………頼むから、もうこんな思いはさせてくれるな。 俺の心臓を止めたくはないだろう? 」 「すまぬ………ミロ……昨夜お前に抱かれていて、こんなに幸せでいいのかといつものように思ったとき、ふとあの時のことが思い浮かび、二度とそんなことがないようにと願ったのは覚えている。 ほんとに軽く考えただけだったのに、心を掠めただけのその意識が心理下に残り、数時間後に発現したのだと思われる。」 「………お前ね、あっさり言ってくれるが、いくら黄金聖闘士でも小宇宙の使い方を誤ると身を滅ぼすもとだぜ!自分を凍らせてどうするんだ? 俺がいないときにそれをやって、もし回復しなかったら二度と俺に抱かれないんだからな、この俺に抱かれないなんて、もったいな過ぎると思わんか?」 冗談を言っているようでもミロの目は笑ってはいない。 それがわかるだけに、カミュの胸は後悔で満ち溢れるのだ。 「本当に今度のことではお前に心配をかけた。 もうプロテクトはかけぬ、解除することを約束する。」 「……え? プロテクトってなんのことだ?」 「ああ、お前にはまだ言ってなかったかもしれぬ。 お前の持つ小宇宙とは違って、アクエリアスの凍結系の小宇宙は防御的機能を併せ持ってもいるのだ。 そこで、いつなんどき聖域に緊急事態が発生するかもしれぬゆえ、たとえ睡眠下にあろうとも緊急時には通常時の80%の度合いで小宇宙を発現することにしているのだ。」 「え?! そんな話は初めて聞いたぜ? ずっと前からそんな……え〜と、プロテクトをしてたのか?」 ミロは呆れた。 たとえ眠っていようとも、聖域に冠たる黄金聖闘士ともあろう者が緊急事態の発生に対処できぬはずはあるまい。 もし俺に抱かれて夢中になってるとしても、俺たち黄金聖闘士は光速で行動できるんだぜ どんな攻撃にもすぐに対応できるだけの能力は持っているじゃないか それに、余計な邪魔者が入らぬように結界も張ってある 未知の敵が攻撃してきてもすぐには届くはずもない そんなパトリオットみたいな、即時対応型小宇宙を準備しておく必要がどこにある? もっと気楽に俺に抱かれてていいんだよ、論理なんか振り捨てて、もっと情理に走って欲しいね、まったく! 自分に黙って、そんな防衛措置をやっていたのかと思うと、慎重さも度が過ぎるのではないか、だから今度のことのような不測の事態を招くことになったのだ、と言いたいのをぐっとこらえるミロである。 「うむ、プロテクトは必要だった。 以前の私ならばそんなものは不要だったのだが、生還してからは……その……ミロ、お前の……」 なんだ? なぜ、赤くなって口ごもる必要がある?? もしかして、生還してから小宇宙の制御が効かなくなっているのか? そんなことが外部に漏れたら、黄金聖闘士の名が泣くぜ! 氷河の力量などまだまだお前の足元にも及ばんから、お前が降格されてあいつが黄金になることなど有りえんが、 それにしても自分の小宇宙を制御できないとしたら、そいつはまずすぎるぜ……… まてよ? 今カミュは俺の名前を出さなかったか?……… なんでだ? 「ん? 俺がなにか関係あるのか?」 なにげなく訊いたのだが、その答えはミロを赤面させるに十分だった。 「その………お前が私をよりいっそう大事にしてくれるのは本当に嬉しいのだが……」 声がだんだん小さくなり、カミュの様子が消え入るようになってきた。 「生還してからは、通常の状態ならすぐに目覚めるはずのわずかな異変にも気付かぬことが多いのだ……たぶん、あの……」 蚊の鳴くような声にミロは耳を澄ました。 「毎晩……その……お前に愛されすぎて……そのため眠りが深すぎて……あれでは緊急時に対応できない……そのためプロテクトをかなり強くかけていた。 それが今回は裏目に出て以前の記憶と混在し、自分に凍気を発動したのに違いないのだ。」 「……え?」 愛されすぎてって………俺のせいなのか? ほんとに? 愛に限度はないと思うんだが、俺としてはごく普通にカミュを……その…可愛がっているだけで…… え? え? ほんとにそうなのかっっ? 真っ赤になったミロが言葉を探しても、ふさわしい言葉など見つかりはしない。 「そっ、そんなことを言われても……いったいどうすれば……俺としては、その、お前を……」 「ほんとに心配をかけた。 次からは今までのように夢中にならないように注意するから……お前には迷惑をかけぬようにする……」 恥ずかしげなカミュに腕の中でそう言われてはっと気付いたミロが、慌てて口をはさんだ。 「だめだっ、いいから、そのままでいいから! 今まで通りでいてくれ!お前は夢中になってくれていいんだよ、遠慮なんかしてくれるな! 俺が結界を張っているし、眠るときも残留思念をうまく使って、もっと安全な防御システムを施すことにするから、お前はなにもしないで安心して俺に抱かれてくれないか、頼む、そうさせてくれ!」 「でも、それではお前の負担が大きすぎる。 申し訳なくて……」 「そんなことはないから、カミュ………なにも心配せず、俺に抱かれてていいんだよ、ほら、こんなふうに……」 やさしく抱きなおされたカミュがいつものように頬を染め、ミロもやっといつものペースを取り戻したらしい。 次々と与えられる甘い口付けにたまりかねてもらされる吐息は、以前のままに芳しいのだ。 「ねえ、カミュ……思い出したんだけど……」 「え…? なにを?」 「今日はバレンタインだ。」 くすっと笑ったミロに耳朶を含まれたカミュが、あっという顔をした。 「俺たちさ……もう16時間くらいこうして抱き合ってるんだぜ、こういうのを世間じゃ、熱々っていうんだよ。 バレンタインの過ごし方としては模範的といえるな。」 「あの……ちょっと恥ずかしくないか?」 「そうか? 俺はいいと思うぜ、お前はどうなの?」 悪戯っぽく見詰められたカミュが恥じらってうつむくのをミロはたとえようもなく可愛いと思うのだ。 「お前がよければ……それでもよい……」 「それじゃ、これからもよろしく。」 「えっ! このまま朝まで……こうして……?」 「違うよ、いくらなんでもそれはない。 もう少ししたら、起きてシャワーを浴びる。 それからバレンタイン用に買っておいたワインを開けて食事をしようぜ。 それからちょっと散歩でもしたら暗くなるだろう? そしたら……」 「……そしたら?」 カミュの耳朶が朱に染まっている。 「知れたこと! 夜だからお前を抱いて寝る。 ほかに質問は?」 「……ない」 艶やかな髪ごとカミュを抱いたミロが唇を重ねていく。 「朝まで寝かさないぜ、いい?」 「お前がよければ……」 「そうこなくちゃ。」 シャワーを浴びるまでにはまだ時間がかかりそうである。 こうして二人のバレンタインが始まったのだった。 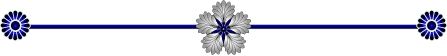 雨降って 地固まる、のたとえの通り、お二人の仲は磐石のご様子。 もはやバレンタインにチョコレートは不要のようです。 この分では夜が明けるまで閨中だったりして? さすがに昨夜の小宇宙疲れで、ミロ様すぐに寝ちゃうと思うんですけど? 「果たしてそうかな? そんな やわな俺ではない。」 「私も期待しているぞ。」 「……え? え〜〜〜っ!」 おまかせいたします、どうぞごゆるりと。 |