「 沐 浴 」
燕を水難からお救いくださったカミュ様のお帰りが嬉しくてならないが、気になるのはお手のお怪我のことだ。
「カミュ様、お手をどうなされました?」
翠宝殿に入ってすぐにお尋ねすると、
「これは鉄砲水といって………あ、貴鬼は知らぬであろうな。 なんの前触れもなく川の上流から矢のような速さで泥流が流れ下ってきて全てのものを押し流してしまうのだが、それに夜中に襲われてそのときに岩にぶつけたのだ。
途中の村で仮の手当ては施してある。」
「ああ、そんな恐ろしい目に……! じきに昭王様より侍医が遣わされて参ります。
きっとよいお薬をいただけます!」
「うむ、貴鬼にも心配をかけてすまなかった。」
カミュ様はさらりとおっしゃるけれども腕に巻かれた布には血が滲んで見えるのだ。
怪我をなさってから何度も取り替えたに違いないのになかなか血が止まらなかったのは、きっと傷が深いからに違いない。 昭王様もどれほどご案じなされたことか。
はらはらしながらお部屋に入ると、、カミュ様が金色の櫃のそばにお寄りになった。
「少し離れているように。」
と言われて、なにがなんだかわからないながら入り口あたりに控えていると、急にカミュ様の周りが明るい金色に輝いてまばゆい光に目がくらんだ。
「カミュ様っ、カミュ様っ、どうなされました?!」
驚いて大声を上げ、やっと目を開いてみるともう金の光はどこにもなくて、カミュ様が身につけていらした金の鎧は影も形もないのだ。
「……あれ?」
びっくりしながらカミュ様が肌着だけを召されているのに気付き、すぐに単衣をお持ちする。
帯を締めて差し上げながら、
「あの、さっきまで着ていらした鎧は?」
とお尋ねすると、
「あれならば、この櫃の中に。」
そう言ってにこと笑っておられるカミュ様はやっぱり神仙に違いない。 普通の人間にこんなことができるはずはないのだから。
そこへ侍医が案内を請うてやってきた。 昭王様の侍医は格式が高いので侍僕を三人くらい連れているはずが今夜は一人なのは、翠宝殿に余分な人数を入れないための昭王様のお考えなのだろうと思う。
「まことに恐れ入りますが、お腕の傷を拝見いたしたく罷りこしましてございます。」
カミュ様の前に進んだ侍医が深々と拝礼し、頷いたカミュ様は手近の椅子に掛けられた。
侍医が言うより先にカミュ様がお袖を肩の辺りまでたくしよせ、腕に巻いた布がはっきりと見えるようになる。
「貴鬼殿は灯りを持って照らしていただけますかな。」
そう言われて手に持っていた灯りをどきどきしながら寄せると侍医がそろそろと布をほどき始めた。
だんだんとお腕の傷が見えてくる。
あっ……!
大人の手のひらくらいの大きさにひどいすり傷があり、熟れた幡桃のような色に腫れている。 その真ん中あたりにぎざぎざに裂けたあとがあり、もう血は固まっているけれど、ひどく痛そうで思わず目をそむけたくなった。
ぎゅっと締め付けてあったので傷は閉じているがいつまた開くだろうと思うと恐ろしい。
カミュ様のきれいなお身体にこんな恐ろしい傷がついたのがつらくて悔しくて心臓が縮む思いだ。 昭王様はご存知なのだろうか。
「一応ふさがってはおりますが、これはあまりに傷が大きゅうございます。 もう一度開きますとなかなか血が止まりませぬので、念の為にお縫い申しあげましょうか?」
「いや、これからはけっして動かさぬゆえ、それは遠慮したい。 傷の中は清水でよく洗い、土や砂などは取り除いてある。」
「それは ようなされましてございます。 では膏薬を持って参りましたので日に三度おつけなされませ。」
カミュ様は傷の手当のことにも詳しくていらして、悪化しない限りはあとは自分で毎日の手当てをするとおっしゃった。
それでもお一人ではきちんと布を巻くことは難しいので、思ったよりも傷の様子がよかったのにほっとしたらしい侍医に薬のつけ方や布の巻き方を丁寧に教わって責任の重さをひしひしと感じてしまう。
「このあと沐浴をなされるのですが、傷を濡らさなければ大丈夫でしょうか?」
心配になって訊いてみる。 毎日の沐浴を楽しみにしていらしたカミュ様だけれど、お出かけになられてからはそれも叶わなかったに違いなく、なんとしてもきれいなお湯でお身体をお清めして差し上げたいのだ。
「さようであられますか………」
侍医が考え込んでしまったのは、本当はお湯に入らないほうが傷のためにはいいからに違いない。
それはとても困ったことで、やっと天勝宮にお戻りになられたカミュ様がいちばんなさりたいことは、ゆっくりおやすみになることと、その前にお湯をお使いになられることに違いないのだ
「それでは、貴鬼殿がお助けして傷をけっして濡らさぬようにできましたら、よろしゅうござりまする。」
「気をつけよう。」
「はい、必ず!」
「お湯はぬる湯を用い、あまりお身体を温めませぬよう。 血流が盛んになりますと、傷にさわるやもしれませぬ。」
「心得た。 それから、侍医殿、頼みがあるのだが。」
「はい、なんなりと。」
「傷の詳細は昭王には内密に願いたい。 あえて奏して宸襟を悩ませるわけにはいかぬ。」
「は…」
このあと昭王様から侍医にお尋ねがあるのは知れたことで、カミュ様の頼みごとには侍医も困ったことだろうと思う。
「傷を縫わなかったことを伝えてもらえば、昭王も安心なされよう。」
困り顔を見たカミュ様がさらに言葉を重ねられた。
ああ、そうなのだ! 縫うほどの傷でなかったとお知りになれば昭王様はきっとご安堵なされるに違いない。
そのために、本当は縫ったほうがいい傷なのにカミュ様はお断りになられたのだ。
いかにもほっとしたらしい侍医は、あとで桔梗の根を煎じた薬湯をお届けにあがりますと言って帰っていった。
「桔梗の根とは?」
「化膿止めに効くのだとか。 手にお怪我をなさったシュラ様も桔梗の薬湯を飲んで直されたと聞きます。」
右手を無くされたシュラ様のお怪我に比べれば、カミュ様のお怪我が軽いことは間違いないのだ。
それを考えて少し心を慰めた。
「カミュ様、それではお湯殿に参りましょう。」
「うむ、貴鬼が手伝ってくれれば傷を濡らさぬことなどわけもない。」
「痛みますか?」
「少し。 たいしたことはないが。」
ほんとに少しだけなら、カミュ様は痛いなどとおっしゃりはしない。 きっと、とても痛いのではないだろうか。 はやく直る日が来てほしいと思う。
お湯殿は翠宝殿の中庭に面していて、水音が外に洩れないようになっている造りは他の殿舎と変わりない。
高貴な方々の内向きの御用なので、普通の近衛兵や、ましてや諸官 ・ 宮女が通ることのある外に面した場所に造られることはないのだ。
カミュ様が初めて天勝宮においでになったときにはお湯のお世話の作法がわからなくて困ったものだけれど、それにもすっかり慣れてきて今日もいつもと変わりはしない。
ただ、お腕のお怪我のことが気がかりで、けっして濡らさぬようにしようと思うのだ。
「カミュ様、今日はお手を動かしてはなりませんから、お召し物をお一人ではお脱ぎにならないでくださいね。
きっとですよ。」
そう申しあげてから先に湯の様子を見るとちょうどいいくらいにぬるまっている。
カミュ様は普段から熱い湯はお好みではないし、夏の暑さを考えるとこのくらいが良さそうなのだ。
更衣の間に戻ると、帯だけを自分で解かれてそのままお待ちでいらっしゃる。
「貴鬼に怒られてはならぬゆえ、あとは頼もうか。」
「それがようございます。 もしもお怪我に障りましたら昭王様のお心にそむきます。」
ここにもお湯殿にも灯りが置かれていてあたりをほんのりと照らしている。 カミュ様が単衣をすっとすべり落とし、お肌のものも気をつけてお脱ぎになるのをお手伝いしながらすばやく柔布をお腰に巻いて差し上げた。
初めてのころはこの手順もお互いに様子がわからずおっかなびっくりでどきどきしたものだが、今ではカミュ様もすっかりお慣れになっている。
全部のことをご自分でなさりたかったカミュ様に 「それでは私が昭王様から叱られます。」 と泣かんばかりにお願いしてやっとお世話させていただいたことを思い出す。
「お手を動かすことはなりませんから、お背中のほかもお世話しますのでどうぞそのおつもりでいてくださいね。
いや、とおっしゃっても今日は聞けません。」
最初にそう言うとカミュ様も、
「わかった。 無理はせぬ。 貴鬼の好きなようにするがいい。」
と湯椅子にかけたままでいてくださった。
朝の湯殿は明るくて白いお肌のきれいなことに目をみはるけれども、夜も更けた今は月も朧ろなこともあってお手の傷ばかりが目立つのだ。
それでも仄かな灯りに浮ぶお身体の白さはとても燕では考えられないほどのものだった。
「お髪も洗いますね、お疲れでしょうけれどこのままではお休みになれません。」
どれほどご無理をなさったものか、カミュ様のきれいな髪がずいぶん汚れていてこれでは明日のお目通りもかないそうにない。
左腕を高く上げて首を右側に傾けてくださったので何度もお湯をおかけしてからふのりを水に浸したとろりとした液で何度も何度も洗って差し上げた。 ふのりは海でしか採れない海藻でたいそう高価なものだ。
天勝宮でははるばる渤海から運ばせたふのりをほんの少しの高貴な方々がお使いになっている。
昭王様は大切なお客人のカミュ様にその日からふのりのご使用をお許しになられ、カミュ様は朝夕ふのりで髪をお洗いなさるものだからもとからきれいな黒髪はますます光り輝き、さらに宮女の方々の羨む元となっているらしい。 ふのりを使えない宮女がたはそのかわりに卵の白身や泥を使うけれど、やはりふのりの効き目には敵わないのだ。
「ああ、よい気持ちだ!」
どれほどお気持ちがよかったのか、普段はそんなことはないのに何度もそうおっしゃっるのでこちらもお役に立てて嬉しくなる。
お髪にお湯をおかけすると以前の通りの滑らかさが戻り、白いお背中や肩を流れるように覆うのがほんとうに美しいのだ。
すっかりきれいになられたのでお髪を白布で包んで差し上げてから湯にお入りいただいた。
「この花は?」
カミュ様がお尋ねになったのは湯にたくさん浮べておいた桔梗の花のことだ。
「お出かけの間に紅綾殿の奥庭に桔梗の花がたくさん咲きました。 太后様がお手ずからお摘みになられて桔梗湯にとお届けくださったのです。 きっと今ごろは昭王様も桔梗湯をお楽しみであられると思います。」
「ほぅ、それはそれは!」
ゆらゆらと揺れる桔梗の紫の花は夜目にははっきりとはわからないもののカミュ様の白いお肌にはよく似合いそうだ。
傷に障らないように左手を浴槽の縁にかけながら一つ溜め息をおつきになると、右のお手で桔梗を幾つかお集めになって手のひらにのせて眺めておいでなのがいかにもお寛ぎのご様子で嬉しかった。
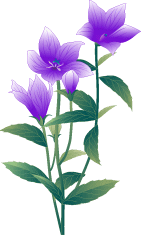
お湯上がりのお身体をきれいに拭いて差し上げて、さて困ったのは濡れたお髪のことだ。 実はお湯にお浸かりのカミュ様はあまりのお疲れから何度もお眠りになられて、お声をおかけしてお目を覚ましていただいたのだ。 お腕が湯の中に落ちてしまったら一大事なのでそっと支えていると、大丈夫だから、とおっしゃるそばから目をお閉じになって頭が揺れる。 ほんとうにお疲れなのだった。
「カミュ様、お髪を乾かすのに時間がかかりますが、お疲れのようですし、横になっていただきましてその間にそっと布を替えて乾かしてみましょうか?」
と言ってみた。 髪が多くていらっしゃるので普段でも十数枚も布を替え、団扇で扇ぎながら乾かすのには相当な時間がかかるのだ。
とても今夜のカミュ様はそれだけの間 起きていられるようには見えないのだ。
「それならば………」
ちょっと首をかしげたカミュ様は楽しげに微笑まれる。
「貴鬼と二人だけの秘密ぞ。 誰にも言わぬように。」
「……え? 秘密って?」
すっと背の高いお姿の後ろから寝衣を着せ掛けていたら、右手でお髪を包んでいた布をお取りになったカミュ様の周りが急に金色に光り輝き、風のような風でないような不思議なものに包まれた。 あっと思うまもなく、濡れていた髪がふわりと舞い上がりその一すじ一すじがさらさらと渦を巻いてやがて肩をゆるやかに覆ったときにはすっかり乾いているようなのだ。
「カミュさま、カミュ様! いったいなにをなさいましたっ?」
あんまり驚いたので腰を抜かしそうになる。 濡れていたお髪がいきなり乾くなんて信じられない!
「驚かせてすまぬ。 いつもは貴鬼に頼むのだが、今宵は少し疲れているゆえ自分で乾かしたのだ。」
「自分で?! あ………ご自分で?」
あんまり驚いたので言葉使いを間違えたのが恥ずかしくて真っ赤になった。
こちらをお向きになったなったカミュ様の前をきちんと合わせて帯を軽く締めて差し上げると、
「ほんとはいつも自分でできるのだが、私の髪の世話をするのを貴鬼が楽しんでいるようなので任せていた。
今日のところは勝手をした。 許せよ。」
と、やさしく頭を撫でてくださった。
すぐのおそばにいたので、お身体を洗ったときに濡れていた自分の服まですっかり乾いているではないか。
さきほどカミュ様は二人だけの秘密とおっしゃった。
ああ、どうしよう!
ほんとは昭王様に隠し事などしてはならないのに、もうたくさんの秘密を持ってしまった!
ほんとはひどい腕の傷のこと、不思議な髪の乾かし方、お湯殿でのなにもお召しでないお美しいお姿、それからそれからほかにもたくさん。
カミュ様って、本当に素晴らしくてちょっぴり困らせられる方なのだ。
「あの……カミュ様…」
ご寝所までお供しながら言ってみた。
「ん? なにかな?」
言えないっ、やっぱり言えない。 好きです、といいたいけれどやっぱり言えない。
「なんでもないです。」
真っ赤になって首を振ると、カミュ様が手をつないでくださった。 それはとても暖かくてやわらかいお手で。
カミュ様が大好きだ!
そう思いながらこれからのお世話を心に描いたことだった。