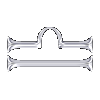
第四夜 老師 「ミロ、明日の午後に老師が到着されるので、そのつもりでいてくれ。」 朝食後にフロントで宿の主人と話をしていたカミュが振り返ってそう言い、俺はかねて用意の飛び切りの笑顔で頷いた。 「ほう! で、どのくらいご滞在になるんだ?」 「それはまだわからぬ。 部屋は私たちのところにお泊りゆえ、何日おられようといささかも困るものではない。 ここの湯がお気に召されれば、長逗留もあるやもしれぬ。」 「そういうことだな。」 九月も半ばを過ぎた北海道は、肌寒い朝が続いている。 今朝の気温も13度と低めで、寝床の中のぬくもりを手放しかねた俺は、カミュを抱きしめたまま朝食ギリギリまでねばっていたのだった。 「ミロ、もうよさぬか! 早く起きぬと朝食に遅れる!」 「俺の朝食は、お・ま・え。 カミュ、もう一度くらい、いいだろう?」 「また、そんなことを……! いいかげんに……あ……ミロ……ほんとに私は………」 「黙って俺のいうことを聞いて。 お前だって、内心では……」 「そんな……そんなことは私は……ああ……いや…………ミロ…」 「もっと…もっと俺を愉しませて………お前は最高の食前酒だよ……」 「………」 そんな経緯があって、朝食の席に着くのは10分遅れたのだった。 老師が来るとなると、またカミュを抱けん日が続くわけだ、くそっ、面白くもない! 肌寒くなったこの季節こそ、抱き甲斐があるんだよ、さっきも最高だったしな 明るくなってるから、さらに恥じらってるところがまたなんとも言えん 少し涼しすぎる風に吹かれながら回廊を通ってゆくと、ナナカマドの葉がわずかに色づき始めて秋が来ていることを教えてくれる。 十月になると緑の葉の中に赤い実が目立つこの木は、白樺と並んで北海道を代表する木なのだ。その白樺のほうは白い幹が夏をイメージさせるが、実は秋の黄葉も実に見事なのだった。 「白樺の木肌の白さはお前の肌に匹敵するな、もっとも滑らかさは圧倒的にお前が勝っているが。」 「よくそんなことを考え付くものだ、それをいうなら、白樺の黄葉はお前の髪に匹敵するというわけか?」 「うん、それ悪くないな! でも、俺の金髪は一年中お前を楽しませてるから、やっぱり俺の勝ち。」 宿の庭にはナナカマドも白樺も植えられていて、四季の移り変わりを俺たちに教えてくれる。 植物の少ない聖域から来た目には、なんとも贅沢な眺めなのだった。 夕食の酒はすこし控え目にしておいた。 「もう飲まぬのか?」 「ああ、明日から老師が来るだろう? 今夜は、ゆっくりしたいから。」 意味を悟ってうつむいたカミュの耳朶が真っ赤に染まり、ちょっと俺を慌てさせる。 「おい、それじゃ目立ちすぎるぜ、抑えられないか?」 と言ってはみたものの、さしものアクエリアスも自分の血流調整は専門外らしく、自分でも困り果てているようだ。 「少し飲めばいいさ、そしたら赤くなるからおなじことだ。 盃半分ならかまわないだろう?」 あまりの酒の弱さに、いつもの食事時には形ばかり付き合うだけで、唇を湿らせるくらいが関の山のカミュなのだが、目立つのを怖れたのか勧められるままに一度に盃を空ける。 「どう? 久しぶりだったけど。」 「ん……なんとかなると思う。」 ちょっと眉をひそめながら、カミュが一つ溜め息をついた。 そして、確かに 「 なんとかなった」。 離れに戻る途中から身体が重くなったようで、なんとなく動きが鈍いようにみえるのだ。 「歩ける?」 「うむ…」 まっすぐに歩いてはいるものの、玄関を入ったとたんに式台にふらふらと倒れこみ、まさかと油断していた俺をおおいに慌てさせた。 「大丈夫か?!」 熱を帯びた身体を抱きかかえて奥まで運び帯を緩めてやると、火のように熱い吐息が俺を迎えてくれて、これではこっちの心臓も高鳴ろうというものではないか。 灯りを落としてそっと寄り添おうとしたときだ、 「ミロ………抱いて…」 しなやかな腕が伸ばされて俺の首に絡み付いてきた。 「カミュ…」 「早く………私が眠ってしまわないうちに早く……」 気にしていないようでいて、やはり明日からの老師の滞在が心に作用しているのだろうか、カミュから俺にせがむというのは相当に珍しいことなのだ。 それ以上の言葉も聞きたかったが、それはあとのお楽しみにすることにして、やさしく口付けながら浴衣の襟をゆるめて白い胸をのぞかせる。 「ふふふ……まるでナナカマドみたいだ。」 「……え?」 「早くも実が色づいてるぜ。」 「あ……」 あとはもう恥じらって声もないカミュをいつくしむのみなのだ。 たったあれだけのアルコールが与えた影響はかなりのもので、幸い眠り込むこともなく、俺は一味違ったカミュを存分に愉しんだ。 たぶんカミュもそうだったと思う。 或いは酔いを免罪符にして、意識的に俺にせがんだのかもしれないが。 明日からはしばらく抱いてもらえないという想いが、きっと意識の隅にあるのだろう。 今までにないカミュの積極性が俺を瞠目させ、切なく甘い声はいつまでも俺を求めてやまないのだ。 「カミュ………すぐにお前を抱ける日が来る………それまで俺のことを忘れないでいて……」 「どうして忘れることがあろう……私のミロ……」 艶やかな髪の乱れもかまわずに俺にすがり付いてくるカミュがいとおしくて、朝まで寝もやらぬことだった。 翌日のことだ。 朝食後の散歩から戻り、離れでくつろいでいるとやってきたのは美穂だ。 いつものようにカミュが応対しているのを俺はなんということもなく横で聞いていた。 「ミロ、来客だそうだ。」 「ふうん、午後だと思ったが、もうご到着か。」 「老師ではない。 どうやらムウのようだ。」 「なにいっっ!」 俺はいやな予感がした。いや、予感などという曖昧なものではなく、厳然たる事実を突きつけられたといっていいだろう。 「ということは……」 「うむ、間違いあるまい。」 全身の力が抜けるようで、まだ何もしていないうちから気力が萎えるような感覚に襲われる。 「なんだって、こんなときに…」 がっくりと肩を落としていると、美穂に案内されてムウ本人がやってきた。 「お邪魔します、お二人とも元気そうですね。」 「だいぶ留守にしているが、聖域に変わりはないだろうか?」 「ええ、平穏無事です。 なかなかよい宿ですね、ミロ。」 美穂が出した煎茶と六花亭の菓子を優雅な動作で口に運ぶムウは、悔しいほど落ち着いている。 「ああ、そうだな。 で、今日の用事は例のあれか?」 「ええ、そうです。 すみませんが、今度はミロ、あなたの番なので。」 俺は聞こえない程度に溜め息をつく。 「そのうち来るとは思ってたさ。 その茶を飲んだら、さっそく行こう。 鉄は熱いうちに打て、と言うからな。」 「鉄ではありませんが、聖衣修復にはふさわしいことわざですね。 では、カミュ、ミロをちょっとお借りします。」 にっこり笑って立ち上がったムウに続いて、俺もカミュに軽く手を振ってから玄関を出た。 ホールにいた美穂にちょっと合図をしてから外に行き、人目のないところで一気に聖域までのテレポートに入るためだ。 「いいところですね、日本にはいつまで?」 「とくに決めてはいない。 慣れれば、日本食もなかなかいいぜ。」 牧場へと向かう道を少し歩いて白樺林に入ったあたりまで行けば、誰の目にも触れない。 次の瞬間、俺とムウは白羊宮の一室に立っていた。 「暑いな!」 最初に感じたのはそれだ。 「今日は29℃、聖域では平年並みの気温です。」 さっききまでいた登別は15℃くらいだったはずだから、その差は大きい。 「そんなものだったかな、まあいい、早くやってくれ。」 俺は作業室とおぼしき部屋の中央に置かれている聖衣の山に歩み寄った。 「あれ? この聖衣は…!」 「ええ、天秤座の聖衣です。 老師がしばらく聖域を離れられるので、その間に修復を依頼されたのです。」 「ああ、そう………」 しばらくって、どれくらいのつもりなんだ? それにしても、ライブラの聖衣とは思わなかったぜ……… 「これが冥界戦で傷ついた聖衣の最後の修復になります。 老師が、若いものの聖衣を先に修復するようにとおっしゃったのでこの時期になりました。」 その声を聴きながら俺は手首を軽く切り、黄金に輝く聖衣の上にかざした。見る間に 鮮血が滴り落ちて、聖衣に新たな生命の輝きを与えてゆく。 自分の血なのにまるで他人事のようで、不思議な気分になるのはいつものことなのだ。 何度も経験してはいるものの、やがて五体が冷えてきた。 血の気が引く、というのはこんなことをいうのだろうと思う。 自分ではしっかり立っているつもりでも、いつの間にか上体が傾いていたらしく、 「ミロ、それで十分です。」 かたわらで様子を見ていたムウに腕をつかまれ、脇のいすに座らされた。 即座にムウが上を向けた傷口に手をかざし、鮮血を流し続ける傷口に治癒術を施すと、みるみるうちに傷口が跡形もなく消え失せるのもいつものことだ。 「気分はどうです?」 手に残っていた血痕を拭き取りながらムウが心配そうに言う。 「ああ………こんなものだろう……もう帰っていいか?」 「いいえ、それはお勧めできません。 自宮に戻るならともかく、日本までのテレポートは負担が大きすぎるのです。 カミュのときもここで数時間休んでもらいましたからね。 」 「……どうしてもだめか?」 俺は恨めしくなった。 いつ老師が宿に来るか知れたものではないし、万が一、入浴のしかたがわからぬ、などと言い出してカミュを誘ったらと思うと気が気ではないのだ。 「無理です。 私が責任を持ってバイタルチェックをしますので、しばらく横になっていてください。 今後聖域にいるのならともかく、遠い日本に行かれては、急変したときに手の打ちようがありませんから。」 「急変……なんて有り得るのか?」 「血液の流量が半減したので血圧が急降下しています。 その影響を最小限にとどめようと、貴方の心臓は拍動を強めて血を全身に送り出そうとしていますが、いかんせん血がここまで減っていてはそれも追いつかず、心臓には大きな負担がかかっているのです。それに身体の各部に酸素を運ぶ赤血球も半減していますから、 酸素の供給もひどく不足しています。 これはけっしていい状態とはいえません。 もしも日本で容態が悪くなって病院にでも運び込まれようものなら、低血圧症状のうえに血液量が少ないのが知れて、日本中の循環器の専門医が駆けつけてきて学会報告ものになるのは確実ですよ。 体重の7.7%が血液量ですから、ミロ、あなたの場合は約6.5kgの半分の3㎏強、つまり3000CCもの血液が不足しているのです。 病院で一般人の血液をそれほど輸血されるのは、黄金聖闘士として望ましいとはいえないでしょう。」 この説得力のありすぎる話に、俺はあっさりと主張を撤回することにした。 そんなことになろうものなら、根掘り葉掘り事情を聴かれたうえに、入院したまま離れへも帰れず、カミュと離れ離れにさせられるに決まっているからだ。 それに、今後も聖衣の修復に使うはずの血に、他人の血液を入れるわけにはいかないのだった。 「わかった、ここで休ませてもらおうか。」 「そうしていただけると、こちらも安心です。」 立ち上がって隣の部屋に行く間も、倦怠感に襲われてなるほどまともに歩けたものではないのだ。 ムウにベッドに押し込まれると、隣から聞こえてくる修復の物音を子守唄代わりにすぐに眠り込んだようだ。 「ミロ、そろそろ戻りますか? いまのところバイタルも安定していますし、日本ではそろそろ夕食の時間になるはずです。」 ムウの声が遠くから聞こえてきて、俺は目を開けた。 見慣れない天井が視界に飛び込んできて、一瞬どこにいるのかわからなくなる。 「あ……ああ……そうさせてもらおうか。」 「では、もとの林までご一緒しましょう。」 ムウに助け起こされて、身体を軽くささえられたまま白樺林にテレポートすると、寒気がいきなり襲ってきた。 「15℃の気温の差は大きいですね、30℃に慣れた身体にはますます負担かもしれません。 くれぐれも無理はしないようにお願いします。」 宿の玄関まで来るとカミュが待っていてくれた。 少しの間だったのに、なんだかとてもなつかしく思えるのは不思議なものだ。 ムウと少し話してから別れを告げ、ゆっくりと食事処へ向かう。 「で、老師は?」 「さきほど見えられた。 一足先に夕食の席にお連れしてから、お前を玄関で待っていたのだ。」 「……湯はこれからか?」 「うむ、離れで美穂の淹れてくれた茶を飲みながら囲碁の話をしたところ、たいそう楽しみにしておいでだ。」 「ああ……囲碁ね…」 すっかり忘れていたが、カミュは宿泊していた老人に碁を教えられて以来、老師の相手をするのをそれなりに楽しみにしていたのだった。 食事処の暖簾をくぐりながら、俺はいつもの席に向かった。 「ご老体にはふさわしい過ごし方だな、俺はどうせ寝てることが多そうだから、茶飲み話でもしながら二人で楽しくやってくれ。」 「そのことだが、ミロ、老師は……」 その途端、いつもの席に目をやった俺は立ちすくんだ。 ぽかんと口を開け、ただでさえ少なくなっている全身の血が頭に上ったみたいで気が遠くなりそうだった。 「やあ、ミロ、久しぶりじゃな!」 張りのある声で俺を迎えたのは、童虎、243年前の聖戦を生き残った伝説の聖闘士の若き姿だった! 茫然としている俺を引っ張って椅子に座らせてくれたのはカミュだ。 「ミロ、驚いただろうが、老師は初めての日本旅行をお楽しみになるため、アテナの許可をいただいてこのお姿でお越しになられた。 宿帳にも 『 童虎・十八歳 』 とお書きになられたので、そのつもりで頼むとのことだ。」 「あ……ああ……そういうことか……わかったが……しかしなぁ……」 てっきり年寄りのご老体と対面すると思い込んでいた俺には、いささか衝撃が大きすぎる。 だいたい、童虎となにを話せばいいんだ? 年寄り向けの話題に、温泉の効能や冷え性の予防法なんかを仕込んでおいたんだが、この若さでは不必要だろう! といって、冥界戦の話は場違いとしか思えんっ! 見かけは十八歳で俺たちより下だが、実力も経験も俺たちをはるかに凌ぐのだぞ! 「まあ、飲め!わしの聖衣に血を提供してくれたそうじゃな、すまぬことだったのぅ。」 外見と言葉のギャップがありすぎて、なんといっていいのかわからない。 すすめられるままに一杯飲み干し、合鴨のスモークを口に入れる。栄養を摂らなければ倒れそうな気がしたし、そうでもしなければ間がもたないような気がしたからだ。 以前に俺がしたように、カミュも栄養価の高い献立に変えてもらったらしく、他の客には海鮮の炭火焼がでているところを俺たちには牛ヒレのステーキが供されているのが有り難い。 「やはり、食事は若くなくては面白くないのぅ、自分の歯で噛みしめてこそ味がわかるというものじゃ!」 そう言いながら、アワビの刺身やら、タラバガニの香草焼きやら、胡瓜と蛸のはりはり和えを食べる老師、いや、童虎は幸せそうで健啖振りを見せてくれるのだ。 考えてみればもっともで、聖域で童虎の姿でいては違和感がありすぎるし、なにも旅先に来てまで年寄り扱いされる必要はさらさらないのだ。 都合のいいことにカミュが囲碁の定石の話を始めたので、俺も栄養摂取を心がけることにした。 なにしろ、今夜はこなさなければならない重要なイベントが控えているのだったから。 離れに戻るといつものようにフトンが敷かれていた、 と言いたいところだが、そうではなかった。 「おい、どういうことだ? 俺たちの寝るところはここか?」 カミュを襖の陰に引っ張り込んで小声で訊いてみる。 「当たり前だ。 老師は目上のお方だ。 床の間付きの十畳間にお休みいただくのは人としての道であろう。 我々は、こちらの次の間に休む。」 「ああ………そう…」 カミュはなんとも思わないのかもしれないが、奥の間は俺たちの愛の巣で、いままでやってきたデスマスクもサガも足を踏み入れることさえしていない。 日中は次の間に座卓が用意されるので、茶を飲むときもそちらを利用していたのだ。 昨夜も俺がカミュを存分にいつくしんでいたその部屋に老師が泊まるなどとは考えもしなかった俺は、つい小宇宙が残留していないか探ったほどだ。 「ほぅ、わしが奥の間でよいのか? すまんのぅ。」 すまん、と言いながら床の間を検分する童虎は満足そうである。 「ところで、さっそく温泉に入りたいのじゃが。」 「それならば、わたくしが…」 「まて! それは俺の役目だ!」 カミュを押しとどめた俺はずいっと前に出た。 誰がなんと言おうと、カミュと童虎を一緒に風呂に入れるわけにはいかんっっ! 「しかしお前は血を提供したばかりで……」 「そのくらいは平気だ、スコーピオンのミロを見損なってもらっては困る! 我々黄金聖闘士の大先輩である老師のお背中をお流しする役目はこの俺が引き受けると、ずっと前から決めていたのだからな!」 童虎は面白そうに俺たちの会話を聞いており、俺の意図が読めているカミュは諦めたらしく、童虎のために浴衣とタオルの用意を始めた。 「サガから少し話は聞いているが、なにしろ初めてのことじゃから、ミロ、よろしく頼む。」 「心得ました!、万事、このミロにおまかせください!」 こうして、心配顔のカミュを残して俺と老師は露天風呂へと出かけたのである。 客は誰もいない。 俺は童虎に温泉の薀蓄を傾けながら背中を流すことにした。 さすが十八歳の肌は滑らかで、ちょっと悔しい気持ちになるというものだ。 なにしろ、人間が一番美しく輝く年齢というキャッチフレーズつきなのだからな。 日本の習慣のことなど話しながら力をいれて背中を流していると、少しふらつくような気がしてきた。しかし、ここで弱音を吐いては男がすたる。 なにより、心配してくれたカミュに合わせる顔がない。 「湯の奥に打たせ湯というのがあります。」 「ほぅ、それはどんなものじゃな?」 しばらく湯に浸かっていたあと、気分よさそうな童虎を誘ってみた。 年に似合わず好奇心旺盛で、目に入るものなんでも質問の対象となるので、俺のほうから連れて行くことにしたのだ。 「この石に腰掛けて肩や背中に湯を当てると血行を促進し、筋肉をもみほぐす効果が得られるといいます。」 「なるほど、論理的じゃな、素晴らしい発想じゃ!」 感心した童虎と一緒に肩に湯を当てていると、なんだか身体に力が入らなくなってきた。 いやな予感がして、そっと立ち上がろうとしたときふっと身体が前のめりになり、慌ててバランスを取ろうとしたのだが思うようには動けない。 「ミロっ!」 鋭い声を遠くに聞きながら、俺は湯の中に倒れこんでいった。 「………なんともなくて、まずはよかった。」 「ほんとうにご迷惑をおかけいたしました。」 あれは………カミュの声だ………誰と話をしている………? 「まあ、今後は無理をせぬことだ、養生が第一じゃよ。」 「はい、よくいい聞かせます。」 張りのある男らしい声だな………カミュ、俺をさしおいていったい誰と……? はっと目を開けると、天井のきれいな木目が見えた。 「カミュ……俺は…」 「気がついたか、ミロ。 打たせ湯で倒れて、老師がここまで運んできてくださったのだ。 覚えているか?」 「わしにつき合わせて悪いことをした。 大事ないか?」 「え…?!」 心配そうに覗き込むカミュと老師の顔が目に入ったとたん、すべてのことが奔流のように頭の中に流れ込んできて、俺はもう一度気が遠くなりそうな気がした。 打たせ湯で倒れて、老師に助け上げられてここまで運ばれたというのか? この俺が??? な、なんという醜態っっ!!! いくら血を提供した後とはいえ、この俺が老師の前でぶざまな格好を晒したというのかっっっ!! 黙り込んでしまった俺を哀れんだのか、 「さて、今日はいささか疲れたの。 ちと庭を散歩してから寝るとしよう、いや、ついてこなくても迷うものではない、一人で行ってこようかの。」 そう言って老師が庭下駄をはいて出てゆく音がした。 「すまん……迷惑をかけた……」 「お前が無事でよかった……湯で温められて血管が拡張し、ただでさえ低い血圧がさらに下がったのだ。」 「お前を風呂に入れたくなかったから………」 「それはわかっている……でも、倒れるような真似はして欲しくない」 カミュが俺の手をとってさすってくれた。 とても安心できる気がして、俺は小さく溜め息をつく。 「老師はなにかおっしゃっていたか?」 「若いからといって油断は禁物だと……それから…」 「……それから?」 「ミロはいい男だから大事にしてやれと…」 「…え?」 赤面したカミュがうつむいて黙ってしまい、俺も困って目をそらした。 「ミロ……」 「なに……?」 「老師は……ご存知なのだろうか?」 俺は、なにを?ともいえなくて咳払いを一つした。 いまさら知らぬふりをしてもしかたない。 「よくわからんが……外見はお若く見えても人生経験は豊富な方だ。 きっと酸いも甘いも噛み分けておられるだろう。俺にはそれしか言えん。」 「そうだな……」 突然、カミュが顔を近づけて唇を重ねてきた。手は膝に置いたままで、長い髪だけが瞠目している俺ののどもとに触れるのだ。 やわらかく甘い口付けはすぐに終わり、頬を染めたカミュが立ち上がる。 「外は冷える。 老師をお迎えに行ってこよう。」 玄関の戸が開いて、すぐまた閉まり、一人になった俺は寝床の中で天井を見つめていた。 その後、老師は三週間ご滞在になり、上機嫌で帰っていった。 日中は娯楽室でカミュと碁を打って楽しまれ、時々は露天風呂で手足を伸ばされていたようだ。 その間、俺は碁を横から眺めたり、ゆっくりと庭の散歩をしたりして日を過ごし、ひたすら体力の回復に努める日々を送った。 また、毎日のように北海道名産のイカやとうもろこし、ジンギスカンや石狩鍋に舌鼓を打ち、ついにはカミュを伴って牧場に行き、馬にも乗られて休日を満喫された。 そんなとき俺は牧場の柵に寄りかかって、老師に乗馬のコツを教えるカミュを見ながら一日を過ごしたものだ。 牧場で働く女性達は、久しぶりに来たカミュが若い男を連れてきたというので大喜びで、暇ができると俺の横でにこにこしながら二人の様子を眺めていたのがちょっと面白かった。 若い童虎は俺ともカミュとも違うタイプで、日本人と似た顔立ちだから彼女達にも親しみやすかったのかもしれない。 「では、いろいろと世話になった。 温泉も日本食も実に気に入った! また来てもよいかの?」 ドキッとした俺の様子がわかったのだろう。 「はははっ、冗談じゃ! もう邪魔はせんから、若い者は若い者同士でゆっくりするがよい。 しかし、もう一度、お前達のどちらかが聖衣の修復に血を提供することがあったら、そのときには寄せてもらうかもしれんの。」 ………え? すると、老師………もしや、計画的に聖衣の修復を?? はっとしたが、フロントで老師のチェックアウトをしていたカミュには、どうやら今の言葉は聞こえなかったようだ。 こうして、宿の主人と美穂たちが深くお辞儀をする中を、老師は宿の車に乗ってお帰りになられたのだった。 「もう体調は全回復したぜ。」 「あれだけよく寝て、よく食べればさもあろう。」 「だから、今夜………いい?」 「お前はすぐそれだ。」 「あれ?お前だって待ってただろ?」 「ん……」 回廊を渡ってゆくと、空の色は爽やかな秋色だ。 夏の間あれほどにぎやかだった虫の声も、わずかに聞こえるだけになっている。 「それにしても、老師のご滞在とお前の体調の悪かったのとがうまく重なったので、今回はお前もイライラせずにすんだということだ。」 ちょっと頬を染めて言うカミュは、やっぱりなにも気付いてないらしく俺をほっとさせた。 「そうだな、偶然とはいえ助かったよ。」 今夜はカミュを思いっきり可愛がってやろう やさしく抱いて 甘いキスをして 心がとろけるような嬉しい言葉をたっぷりと聞かせてもらおう 俺は胸を膨らませながら離れに向かっていった。 それにしても、聖衣の修復に血を提供するシーンをこんなにしっかり書くとは思いませんでした。 よそ様では今までに幾つも読んでいたので、 すっかりイメージが出来上がってしまっていて、自分らしさを出すのに一苦労。 この話、最初は老人の老師がやって来て、美穂ちゃんにいたわってもらったりしてたけど、 ミロ様が湯船に沈んだところを、背が高くないと助けられない、との判断で童虎に変身してもらうつもりでした。 でも、書いてるうちに若者の童虎に登場していただくことに。 一度若くなったら、入れ歯ではご飯食べたくないですよ〜って、老師は果たして入れ歯だったのか??? 人一倍健康に気を使いそうだから、歯磨きさえちゃんとしてれば、全部自分の歯だったのかも? でも、年が年だから固いものは無理じゃなかったのかしら? それなら、十八歳の童虎に北海道でいろいろ食べさせてあげよう! と思ったのでした。 |
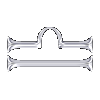
、