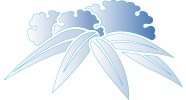
| 有馬山 猪名の笹原風吹けば いでそよ人を忘れやはする |
ありまやま いなのささはら かぜふけば いでそよひとを わすれやはする
大弐三位 ( だいにのさんみ
) 百人一首より
【歌の大意】 私があなたを愛してない、なんてことありませんわ
有馬山のふもとの笹原が風でそよそよとそよぐように
ええ、そうよ、あなたを忘れるはずがないではありませんか
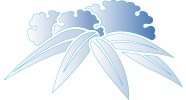
任務を終えたミロが十日ぶりに聖域に姿をみせたのは、もう夕闇があたりを包むころだった。
思ったほどの困難はなかったものの、十日も留守にしたのは初めてのことで、その間、殺伐とした感覚で過ごさなければならなかったミロにはカミュを希求する気持ちが強くなっている。
脳裏にカミュのしなやかな手を思い浮かべながら足を早めたミロが巨蟹宮を抜けようとしたとき、呼び止めたのはその主デスマスクである。
「帰ったか、ミロ!」
「ああ、いま戻ったところだ。」
「お前……誰かに聞いたか?」
「…え? …なにを……?」
いつもならにやにや笑っているデスマスクが妙に真剣な顔をしているのに気付いたミロの心臓が、鼓動を早めていった。
「カミュの様子がおかしい。」
デスマスクは、そう言ったのだ。
ミロが出かけて二日後にカミュに単独任務の指令があり、いつも通りにカミュは静かに出て行った。 そんなことはよくあることで、誰も気にしなかったし、カミュも隣宮のシュラとアフロディーテに 「行ってくる。」 と声を掛けただけだ。 三日後に帰還してきたときも、二人に 「いま戻った。」 と声を掛けて、それだけだった。 いつものことだ。
その後数日間は、誰もカミュに会わずに過ぎた。 これもまたよくあることで、活動的なデスマスクやミロは毎日のように何人もの聖闘士と会うし、その一方、思索を好むシャカなどは半月以上も誰とも接触しないことも珍しくない。 そういうものである。
そして、カミュの異変に最初に気付いたのが、そのシャカだった。
「それで、シャカが俺たちに声を掛けたってわけだ。」
そしてデスマスクが語る話はミロを蒼ざめさせた。
昨日の午後、たまたま教皇庁に用事ができたシャカが重い腰を上げ、宝瓶宮を通り抜けようとしたとき、カミュと出会った。
「……カミュ、近頃、変わったことはなかったかね?」
「別に……なにもないが。」
ただそれだけで、シャカにはカミュの小宇宙の変調がわかったのだという。
そもそも個々人の持つ小宇宙の性質は微妙に異なるものの、その本質はいずれも変わることがない。
平常時の安寧な精神状態にあっても、人が呼吸するのと同じく、小宇宙は活発に動き続けているものだ。
十数年もの間、ともに過ごしている黄金の間では互いの小宇宙については知り尽くしており、特にシャカほどのレベルともなると微細な変化も察知することができる。
そのシャカの見るところ、見かけは普段のカミュと変わらぬものの、小宇宙がほとんど 「
動いていなかった 」 のである。
「それはどういうことだっっ!!!!」
ミロは叫んだ。 額に汗が滲み、足が震える思いがする。
「いったい、俺の留守になにがあったというのだっ??!!」
デスマスクの胸ぐらを掴みかねない勢いに、巨蟹宮の主もたじたじとなった。
「お、落ち着けっっ! 俺たちも出来るだけのことはやった!!」
ミロの小宇宙が不安と焦燥で膨れ上がるのが感じられ、あたりの空気は緊張を孕み今にも張り裂けそうなのだ。
「シャカはすぐさまカミュを静かな部屋に連れてゆくと、時間をかけて丹念に潜在意識から表層心理まで精査してみたそうだ。」
「意識だと?!」
「ああ、カミュの小宇宙の変調は、器質的障害から来るものじゃなくて、心理的原因があるんだそうだ。
どうしてそれがわかるのかは、俺には理解できなかったがな。」
「で、カミュは今どうしてるっっ?!」
声が震えるのを隠しようもなく、ミロはいら立つばかりなのだ。
「宝瓶宮にいる。 ともかく一緒に行こうぜ、道々話していこう。」
すでにあたりは闇色に沈み、麓からの風が足元を吹き抜けてゆく。
「シャカはその場で、できるだけのことをした。 まずいことに、俺たちが異変に気付かずにいた四日の間に症状は進行していたそうだが、おとなしくいうことをきいてくれたので 可能な限り心理の奥まで入り込み、混乱している面を修復したんだそうだ。 もちろんもっと難しい言葉で説明してくれたが、俺にはそっちの方はさっぱりだ。 で、シャカはあらかたの手を尽くしたところでムウを呼び、ムウは途中にいる俺たちに声を掛けながら宝瓶宮に来たってわけだ。」
このころにはミロの手が慣れた扉を押し開けている。 いつもと同じはずなのに、たとえようもなく重く感じられるのは気のせいに違いないのだが。
「で、現状はどうなんだ?」
暗いホールに響くミロの声が心なしか震え、闇の暗さを一層認識させた。 通い慣れ、隅々まで知り尽くしたこの宮の空気が両肩に重くのしかかる。
「一見したところ普通に見える。 もっとも、もとからそんなにしゃべるほうじゃないから、俺にはあまりわからない。
小宇宙の乱れもなさそうだが、シャカとムウは、完全に復調しているとはみていない。
あの二人がそういうんだから事実だろう。 まだ何かが完全な復活を阻害しているのだそうで、
この影響が広がる可能性も否定できんそうだ。」
「原因は…なんだ? ……わかってるのか?」
高い天井に響く足音がやけに大きいような気がして、ミロは声を抑えた。喉がひりつき、舌がもつれる気がする。
「それが、どうやら精神攻撃を喰らったらしい。 カミュが任務地や内容について口を閉ざしているので、シャカが教皇庁に行ってちょいと質問したら、あっという間に回答が出てきたそうだ。 守秘義務なんぞ、シャカの前では無に等しいな。」
「精神攻撃とは……なんてことだ!」
目に見える身体の傷ならなんとでも直しようがあるが、心に負った傷を見きわめ、治癒させるのは難しい。
過去において、精神障害を負って最終的に聖域を去った聖闘士の例はミロも知っている。
「ともかく俺たちにはこれ以上どうしようもない。 シャカの言うには、カミュの心の中の何かが欠損しているらしいんだが、それがなにかは判別できんそうだ。
カミュの心の中になにがあったのか知っている者は本人以外にいないんだから、そのうちのなにかがなくなっていても俺たちにわかるはずがない。
だいたい、十数年の付き合いといっても、よく考えてみるとそんなに深いつき合いじゃなかったからな。
どこがいつものカミュと違うのか、よくわからんというのが実情だ。 しかし……」
ミロは居間の扉の前で立ち止まった。 隙間から廊下にさした細い光があたりの暗さを際立たせ、
中から流れるカミュの静かな小宇宙がミロにその存在を知らしめている。 深く馴染んだ涼やかな小宇宙の中のかすかな変化をとらえようと焦るミロの耳に、デスマスクのためらいがちな低い声が聞えてきた。
「ミロ、お前は…カミュと…その、なんだ……親しいだろう?………なにが違っているのか、なにが足りないのか、お前なら分かるんじゃないのか……?」
デスマスクにカミュとのことを仄めかされたことなど今までになかったことで、こんな事態にもかかわらずミロは頬を染めるのだ。 おそらく言ったほうもそれは同じなのだろうと思われたが、宝瓶宮の暗さはそれを隠してくれた。
「……そうだな…………任せてもらおう。」
ミロが静かに扉を開けた。それに続くかすかな気配に、椅子に掛けていたカミュが振り向き、その瞬間にデスマスクにもはっきりとわかったのだ。 穏やかでほとんど動きの見られなかった小宇宙が急に目覚めたようで、めまぐるしいほどに鮮やかに渦を巻いて流れ出すのは劇的だった。
内から湧き上がる歓びが、表情をなくしていた顔をこれ以上はないほど美しく耀かせ、そんなカミュを見たことのなかったデスマスクを驚嘆させる。
立ち上がったカミュは、まっすぐに歩いてきて、いかにも自然にミロを抱いた。
「ミロ……私のミロ…………私は…忘れてなどいない。」
やわらかい唇がミロを求め、しなやかな手は艶めいた仕草で流れる金の髪を梳く。
「むろんだ……お前が俺を忘れるはずがあるものか!」
融合した小宇宙が部屋に広がり、それはみるみるうちに宮全体を包んでゆくのだ。
抱擁の後ろで、デスマスクがそっと身を引き扉を閉めた。 部屋の中いたカミュには、廊下の暗がりにいたデスマスクは見えなかったのかもしれず、また、そんなことはどうでもよかったのかもしれぬ。
まるで思春期に足を踏み入れたばかりの少年のように頬を紅潮させた影が、高鳴る胸を抑えて長い廊下を遠ざかっていった。
「 カミュ様、精神攻撃を受ける」 篇です。
もはや何も説明は要りますまい
こうしてミロ様は、カミュ様を取り戻したのです。
「デスマスクか?」
「ああ、シャカ。 瞑想中、邪魔するぜ。 カミュのことだが…」
「わかっている。 」
「……もしかして、こうなるって知ってたとか?」
「さあ、どうかな………しかし、これ以上知ろうとは思わない。」
「あ、当たり前だっっ!」
「どうしたのかね? 赤面するなど、君らしくもない。」
「…し、知るかっ!」
上掲の和歌の作者 大弐三位は紫式部の娘です。
この歌はたいそう技巧を凝らしてあり、
結びの 「そよ人を忘れやはする
」 を導くためだけに修辞を重ねています。
「有」 と 「否
(猪名)」 で男女間の愛の応答を暗示し、
笹原のそよぎは 「
そよ 」 という語を導きます。
「 そよ 」 は 「
それよ 」 の省略形、「 いで 」 は 「 さあ 」の意 ( 感動詞 ) です。
有馬山のふもとの猪名の笹原、その笹原がそよとそよぐ、
そうよ、それなんですよ 私はあなたのことを忘れはしませんよ
カミュ様の素顔が垣間見えた一瞬です。