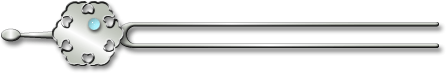
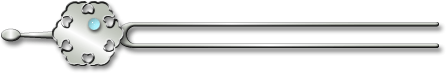
| 駒とめて袖うちはらふかげもなし 佐野のわたりの雪の夕暮れ |
藤原定家 新古今集
【 歌の大意 】 馬をとめて袖に積もった雪を払おうにも
その物陰すらありはしない佐野の渡しの雪の夕暮れであることよ
苦しくも降り来る雨か三輪の崎狭野の渡りに家もあらなくに (長忌寸意吉麻呂)
苦しくも降り来る雨か三輪の崎佐野の狭野の渡りに家もあらなくに (『万葉集』)
〔あいにく雨が降ってきた。三輪の崎の狭野の渡りには雨宿りする家もないことよ〕
一月初めの午後のことだ。 兵学の御進講を終えられた昭王様が不意の野駆けを思し召され、急ぎ厩舎へ使いを走らせることになった。 「供はアイオリアと貴鬼でよい、と云っても通るものではないか。 警護はほどほどにせよ。」 そう仰せられると、侍僕の手を制されて御自ら手早く更衣をなさる。 「貴鬼、参るぞ。」 部屋をお出になろうとしたときに、侍僕頭が濃紫の袱紗を乗せた盆を奉じた宮女を連れてやってきたが、昭王様がお出かけなさるのでそのまま脇に寄って恭しく拝礼をしている。袱紗にちらと眼を向けられた昭王様だが、今年初めての野駆けのほうにお心がお向きなのだろう、そのまま厩舎へと足を運ばれた。 厩舎ではすでにアイオリア様が近衛の兵二十騎とともにお待ちになっておられ、昭王様はお気に入りの鹿毛にこれもご愛用の螺鈿の鞍をお乗せになるとすぐさま御出発なさる。 近衛の兵の指揮をとっているのはシャイナ副将軍の片腕といわれているカシオスで、身体が大きくとても目立つのだった。 「貴鬼、ついてこれぬようであれば、そちに合わせてもよいのだがなんとする?」 「貴鬼ならば御斟酌 ( ごしんしゃく ) なされずともよろしゅうございます。 昭王にはとても追いつきませぬが、このアイオリアに勝るとも劣らぬ乗り手になりましてございます。」 昭王様の前でアイオリア様にそんなふうにお褒めいただくのは初めてで、かっと全身が熱くなる。 街中をゆっくりと抜けてゆく間も、頬の赤さが目立つのではないかとどきどきしてしまうのだ。 厩舎を出た時には薄日もさしていたのだが、いつもの広野に出る頃には雲が全天を覆い、雪催いの空となってきた。 「これは雪になるやも知れませぬな。」 「そうだとしても、ここ何年も積もったことはない。 ちらつくだけゆえ大事ない。」 警護の兵をやや遠くにしりぞけると、昭王様はさっそく馬に鞭をお入れになり、いつも目印になさっておられる彼方の木までアイオリア様と競べ馬 ( くらべうま ) をなさり始めた。 寒さを嫌う魔鈴を天勝宮に残してきているため、馬も恐れるものなく十二分に競い合っているようにも見えるのだ。 「次は貴鬼と走ろうぞ!」 幾度目かにこちらまで戻っておいでになった昭王様に突然そうお声をかけられてどきっとしていると、アイオリア様が笑いながら、 「もしも貴鬼が勝ちましたら、なんとなされます?」 と昭王様におっしゃったので驚いた。 冗談にせよ、昭王様がお負けになるなどあるはずもない。 「さて、その折には余の厩舎から望みの馬をとらせよう。」 「ほう、 これは豪気な!そう聞いては貴鬼も負けられぬぞ、心して走れよ。」 この競べ馬を興深くお思いらしい昭王様と並んで広野を駆けてゆくなど思いもしなかったことで、もちろん勝たせていただくことなどあるはずもないが、身の誉れに手綱を持つ手が震えるほどだ。 アイオリア様の合図で同時に飛び出した馬は目当ての木に向かって矢のように駆けて行く。 しかし、そう思ったのは最初のうちだけで、並んでいたはずの昭王様がすっと前にお出になられたと思ったら、みるみるうちにお姿が小さくなってゆくのだ。 懸命に鞭を入れてもとても追いつくものではなく、木を回って戻ってきたときには二十馬身ほど離されていたに違いない。 「アイオリア、そなたの一番弟子は、まだ馬には手が届かぬな。」 笑いながらそう仰せになる昭王様がふと空を見上げられた。 「これは……もしやすると……」 「いかにも雪にござりまするな。」 アイオリア様のお言葉通りで、空からちらほらと落ちてきたのはこの冬三度目の雪だった。 「やむをえぬ、いま少し馬を責めたかったが帰宮しようぞ。 みなを凍えさせるわけにはゆかぬ。」 そう仰せになりながら昭王様が馬を返されるのを契機にアイオリア様が手を挙げて合図をなさると、遠くに控えていた警護の兵たちが急ぎ寄ってくる。 カシオスが隊列の指示をしている間、昭王様が手のひらに雪をお受けになってじっとご覧になられているので、はっと気がついて畏れながら真似をさせていただいた。 半ば溶けたそれからは、あのきれいな六角形の形を想像することは難しい。 あの時から何度も雪が降ったけれど、一度として美しいあの形が見えたことはないのだった。 昭王様が一つ溜め息をつかれる。 「冬の野駆けは、馬の走りもいま一つぞ。 春が待たれることだ。」 「次の夏までには、貴鬼の腕もさらに上がっておりましょう。」 「夏か………あの時には難儀であったが、真冬の今は、あの日差しも夕立も、いや、雷さえも懐かしくてならぬ。」 そう仰せになりながら天勝宮に向けて駒を進められていた昭王様が、ふと後ろを振り向かれた。 といってもそちらには競べ馬の目印にした木があるだけで、ほかには何もありはしないのだった。 広野を抜けきらぬうちに雪が激しくなり、あたりは真っ白になり始めた。 前を行かれる昭王様の御髪にも御袖にも、雪は分け隔てなく白く降り積もってゆくのだ。 「こんなに早く積もるとは! あいにく雪を避ける物陰もありませず、申し訳ありませぬ。 急ぎ帰宮いたしましょう!」 そう云われるアイオリア様は寒さに頬を白くなさっておいでだが、昭王様はそんなご様子にも見えないのは、ありがたいことだ。 兵たちの中には寒さのために唇を震わせている者もいる。 馬の鼻息も白く見えるほどの寒気なのだった。 その言葉に応じた昭王様が駒足を早められると、御袖の雪もさらさらと吹き飛ばされ跡形もない。 けれども街中に入り、並足になられるとまたもや雪は御袖を白く染めてゆく。 それでも、昭王様が滅多に降らぬ雪をお楽しみなさるご様子は、いつものことなのだった。 「思いのほかの寒さに、兵の身体も冷え切っておりますが。」 武徳門を入ったところで、アイオリア様が馬をお寄せになり意味ありげに昭王様にささやかれた。 「よい、差し許す。 酒 ( ささ ) で存分に暖まるがよかろう。 造酒の司 (みきのつかさ ) に申し伝えよ。」 このご内意に馬をとめたアイオリア様がご恩情を伝えると、近衛二十騎は歓呼の声を上げ一斉に 「 慶福!」 と唱和する。 その地点で近衛の兵とは左右に別れ、うっすらと積もった雪に三騎の蹄のあとをつけながら厩舎に向かって馬を走らせていると、すぐ脇の回廊から魔鈴がぬっと顔を出した。 アイオリア様に厳しく躾けられているので、天勝宮で咆哮したり飛びかかったりすることはないのだが、やはり獅子は獅子である。 突然のことに怖れた馬が跳びはねて、それを抑えるのに手こずってしまったが、昭王様とアイオリア様が平然と馬を御しておられるのには感嘆するのだ。 厩舎で待機していた瞬に馬を預けると、アイオリア様は盛んにじゃれつく魔鈴を従えて獅藝舎へと向かわれた。 お帰りをお待ち申し上げていた侍僕たちとともに昭王様のおともをして紅綾殿に着いたときには、すでに小雪がちらつくだけになっている。 「気の早いことだ。 またも雪景色は望めぬか。」 常のお部屋にお入りになり、寒さを厭われることもなく南面した窓を開けさせたまひて外を眺められた昭王様が雪のやむのを残念そうにお思いなのは、あの日の雪の思い出がお心に深くお残りゆえに違いなかったが、昭王様からお言葉があるまでは誰一人そのことに触れることはない。 昭王様はあの日以来、一言も仰せにはならず、畏れながらそのことでかえって、あの夏を深くお心に刻まれたことが拝察できるのだった。 雪に湿ったお召し物の更衣を終えられたときに、ふたたび侍僕頭がやってきた。 今度は昭王様も、宮女の捧げる盆の上の袱紗をお開きになり中のものを披見なされる。 「 重畳。 二つとも芳春殿に参らせよ。」 仰せを拝承した侍僕頭が退出しようとしたとき、昭王様がお呼び止めになられた。 今一度、袱紗を開かれてそのうちの一つを指し示されると、 「同じものを今一つ誂えよ。」 と仰せになられる。 承った侍僕頭が退出するのと入れ替わるようにして、侍僕が灯りをつけにやってきた。 気がつけばもう夕暮れで、雪明りの望めぬ夜がやってこようとしているのだった。 「貴鬼、そちは雪が好きか?」 昭王様の突然のご下問にどきっとしながら、 「はい、好きでございます。」 そう申し上げると、昭王様は黙って頷かれ、そのまま暗さを増してゆく外を眺めておられた。 カミュ様がお発ちになって三度目の冬のことだった。 |
、
。