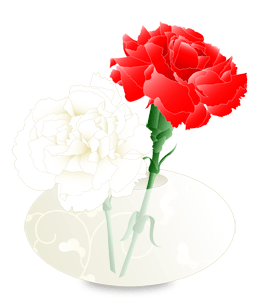
| 母の日 |
娯楽室を出たミロとカミュがホールを通りかかったとき、ちょうど二組の宿泊客が到着したところだった。 一組は年取った母親とその息子らしく、もう一組はまだ元気そうな母親と若い娘二人のようだ。 何の気なしに目をやると、美穂が客の母親の方に赤い花束を手渡している。 「あれ? 珍しいな、泊り客に花束贈呈とは初めて見たぜ。」 「どちらにも渡したところをみると、今日の宿泊者には特別のイベントがあるのかもしれぬ。」 「そういえば、誕生日に泊まっていると、夕食にはワインか大吟醸のサービスがあるからな♪」 そんなことを話しながらふと外を見ると、一台のタクシーがとまり、今度は60歳ほどの小柄な女性が降りるところである。 すると美穂がにこにこしながらお辞儀をし、フロントに案内すると奥の事務室から宿の主人を呼んできた。 主人は嬉しそうにしながら宿泊の手続きを済ませると、その婦人の手荷物を自分で持って離れへと続く廊下に案内していくのだ。 これはとても珍しいことで、通常は美穂たち従業員が客を案内するものなのである。 「ふうん、人手が足りないわけでもあるまいに、主人自らとはね。」 世間はゴールデンウィークで人出が多いのだが、離れが五つだけのこの宿の込み具合は常に変わることがない。 半年先まで予約で埋まっているだけの話で、宿泊客は多いときで十五、六人、少ないときは十人ほどなのだ。 「初心に帰って、接待の基本を再確認するのかもしれぬ。」 初心に帰れ、か………たしかに大切なことだ! 毎晩のことで狎れてきているかもしれんからな、 ひとつ今夜は、初心に帰ってカミュを抱くことにしようじゃないか♪ 一人そう決めると、ミロは早くも歩き始めたカミュのあとを追っていった。 家族風呂のあとで食事処に行くと、驚いたことに、今日の宿泊客に混ざって宿の主人が一番奥の目立たない席に着いている。 一緒に膳を囲んでいるのは、夕刻に一人でやってきた小柄な婦人なのだ。 「おい、カミュ、奥の席を見てみろよ………ここの主人が食事をしてるぜ!」 「ほぅ! 普通では考えられぬが………あ、なるほど! ミロ、あの婦人はここの主人に面差しが似ているように思われる。 もしかしたら母親ではないだろうか?」 「え? そうかな……俺にはそれほど似ているようには思えんが。」 「いや、耳の形がそっくりだ。 たとえほかが似ていなくとも、耳の形には遺伝的要素が強く現れる。 きっと親子に違いない。」 こんなときはギリシャ語で話せるのが、気兼ねなくてよいのである。 噂されていることなど露ほども思わない宿の主人は、婦人から注がれた酒を嬉しそうにして飲んでいる。 そこへ陶板焼を盆に載せた美穂が現れ、なにか言いながら給仕をし始めた。 「ふうん、今日は陶板焼か♪ 最初は驚いたが、慣れれば鉄皿に乗せてあるより風情があって俺は好きだよ。」 「まったく日本の器のヴァリエーションには驚かされる。 その意匠の見事さは他に類例がない。」 婦人と二言三言話していた美穂が戻ってゆき、今度はミロたちに前菜を運んできた。 ミロの手のひらよりもはるかに小さい楕円の器には牡蠣のグラタンが熱々の熱気を上げ、添えられた鮮やかな緑の小さい蓋物には筍の木の芽和えが入っている。 「一つ一つの献立の量が少ないのには唖然としたが、きれいなことは世界一じゃないのか? 慣れてくれば、美味いしな♪ 俺はフランスのものはなんでも好きだけど、料理の方は、味はともかく、器が単調だな。 全部同じ柄の丸い皿ばかりじゃつまらんだろう、日本みたいに季節の花や波や月をデザインしてある食器を使ったほうがなんといっても楽しいじゃないか!」 「日本料理は舌だけでなく目でも食べる、という表現があるくらいだ、見て楽しむというのも大事な要素ということだ。」 ふふふ………食べたときの味はもちろん重大だが、視覚的味わいも重視してるぜ、俺は♪ その点、すべての日本料理をはるかに凌駕するカミュのヴィジュアル・ファクターといったら……! 「なにを笑っている?」 「うん、こんな見事な料理を食べられる幸せをかみしめてた♪」 いくら見事でも、日本人と同じ量では若い二人には物足りない。 そこで宿では二人のためにメインの品に加えて、ステーキなどを出してくれるのがいつものことだ。 もっとも、ソースには毎回工夫がしてあり、大根おろしが使われていたり、山葵風味になっていたりと、それぞれに二人を喜ばせてくれる一皿になっている。 焦がしバターに白ワイン、醤油を加えたソースなどはミロの大のお気に入りなのだ。 牡蠣のグラタンに舌鼓を打ったミロがふと奥に目をやると、店内のあちこちにを見ていた件 (くだん) の婦人と目が合った。 そこは慣れたもので、ミロがにっこり笑って目礼をすると、婦人の方もちょっと遅れながら軽くお辞儀をする。 そのあとは宿の主人とまた話が弾み始めた。 「やっぱり親子かな?」 「まず間違いあるまい。」 「ふうん、俺たちにも他の聖闘士にも考えられんことだが、世間というものはそういうものかもしれんな。」 「親孝行という言葉が、この場合は適合するのかも?」 「ふうん………ますますありえないぜ……まあ、もう一杯いけよ、飲めないとは言わせんぞ♪」 料理が一段と華やかだったせいもあり、ミロはしたたかに飲み、カミュも二杯は空けた。 ステーキが出て来たときにはミロがワインも頼んだので、いっそう酔いが進んだものと見える。 「ミロ、もう戻ろう。 私たちが最後になった。 片づけができぬと、美穂たちも困る。」 「ああ、そうだな…今日はかなり飲んだ……お前、歩いていける?」 「むろん、大丈夫だ。 お前こそ、大丈夫だろうな? こんなところで醜態は見せてくれるな。」 「ふっ、この俺を誰だと思ってる! スコーピオンのミロともあろうものが、まっすぐに歩けないとでも思っているのか?」 なるほど、席を立って歩き始めればしゃんとしたもので、いささかも酔いを感じさせないのはさすがなのだ。 もっとも、赤い顔と早すぎる動悸がそれを裏切っているのだが。 離れへと続く回廊に出ると人目がなくなり、ミロがカミュにちょっともたれかかり始めた。 やはりな……いつもよりピッチが早かったし、ミロにしては珍しい 「大丈夫か?」 「う〜ん……大丈夫といえば大丈夫だが、そうでないといえばそうでもない………」 「なんのことだ?」 「歩いていけるし、気分が悪いわけでもない。 でも………」 「でも?」 「お前を抱けないかも………すまん……期待してた♪?」 「ばかなことを……」 ミロを半ばかかえて離れの鍵を開け、奥の間に敷かれているフトンに寝かせてやった。 「ほんとにごめん……こんなはずじゃないんだがな……まったく…しかたがないな……」 「気にするな。 その代わり……」 「……ん…?」 「お前が私を抱けぬなら、私がお前を抱こう……安心して眠るがいい。」 その言葉はミロには聞えなかったのかもしれない。 目を閉じているミロの横にカミュがすべりこむ。 私には親の記憶はないが、ミロはまだ覚えているのかもしれぬ……… せめて今夜一晩 お前を抱いていよう 外は風が吹いている。 まるで親鳥が雛を囲い込むように、カミュはミロを抱きしめていった。 日付こそ違え、母に感謝する心は全世界共通のようです。 赤いカーネーションも白いカーネーションも、この日は特に耀きます。 ここの壁紙の左に見える紋様は 「 麻の葉 」。 昔から赤ん坊の産着に使われることが多い紋様です。 眠るお二人にも、幸せな夢が訪れますように。 ※ 「母の日」については ⇒ こちら と こちら |
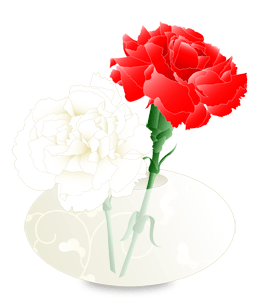
、