鋳物に対するニュートン力学の適用
梅村研究開発事務所 梅村晃由
(長岡技術科学大学名誉教授)
1.適用するニュートン力学と数値計算
隣り合う流体の速度差はせん断力を発生する(ニュートン流体)、隣り合う物体の温度差は熱流を発生する(フーリエの法則)、隣り合う物体の濃度差は成分流を発生する(フィックの法則)。 これらは類似の法則である。それぞれの関与する物理量、すなわち、力(運動量)、熱(エネルギー)、物質(質量)は保存される。その保存方程式は、固体についてよく知られたニュートンの運動方程式と殆ど同じ形である。したがって、一般には認められないかも知れないが、ここでは、これらをまとめてニュートン力学と呼ぶことにする。
鋳物は、鋳型に注いだ溶湯から鋳型に熱が移動することによって、凝固が進行し製品となるので、注湯後の熱と物質(諸成分)移動の過程が重要である。しかし、1960年ごろまで鋳物の研究者は、この過程を伝統的な職人技術(鋳造法案ノウハウなど)に任せ、溶湯の成分と出来た鋳物の組織や強度だけを研究していた。熱移動の方程式は既に完成していたにもかかわらず、鋳物に適用されなかった。それは、信頼できる近似解が得られなかったからであろう。機械の設計などへの適用に較べて、鋳物に適用することが出来なかった理由は二つある。一つは方程式の非線形性(求めようとする未知数yiやその微分dy/dtが、既知の値のみを係数とした和の形とならないこと)にあるが、もうーつは、鋳物の形状が複雑なことである。特に複雑さは、解析的に近似解を求めるのに致命的であったように思える。しかし、その後、これらの困難は、コンピューターの発達で、数値計算によって克服された。
数値計算は、解析解ほど広くは適用できないが、得られる解の計算精度は要求に応じてどんどん上げられる。にもかかわらず、現実の鋳物と合致しない。そこで、熱伝導度、比熱、密度、拡散係数などの物理定数、そして、熱伝達係数、変形抵抗などの技術定数、等の正確さを求め、鋳物がおかれた条件を模擬しで、正確に測定しようとする。が、解決はしない。時には、計算で、実際とかけ離れた物性値を用いた方が、現実に合うこともある。今日では、湯流れと凝固について、実用性のある多くの計算ソフトが市販されている。それらの計算ソフトでは、実物とあわせるために、熱や物質移動の方程式では表現できないような、種々の補正が加えられているものと思われる。
ところで、1975年ごろ筆者が気づいて1)、今も、鋳物計算ソフトに取り入れられていない問題がある。それは、鋳物の凝固の過程で、温度の変化とともに成分の移動が起こって化学反応が進行することである。このことが鋳物の金属組織の形成と欠陥発生の解明の要点と思いつつ、進んだ取り扱いは難しく避けてきた。しかし、先日の編集委員会からの依頼をきっかけに、ふと、再挑戦の意欲が生まれた。そこで、上述のニュートン力学の立場から、基礎方程式を組みなおしてみた。
2.保存方程式の組み立て
まず、鋳物で保存量として注目されるのは、溶湯に含まれる各成分、鉄鋳物であればシリコンやカーボン、アルミニウム鋳物であれば銅やシリコン、外に、水素や窒素や酸素などのガス成分である。もちろん、固相と液相、化合物相も注目される。これらを、一般に、iで表し、i=1,2,3・・を元素または化合物、sを固相、lを液相、gを気相、を意味するものし、添え字iを省略したものを固相液相気相を合わせた全体を表わすことにする。まず、運動量やエネルギーや質量を纏めて、一般に、保存量をYi、その流れをJiとすれば、ものの内部や表面で、保存方程式、

が成立する。これは、単位体積あるいは単位面積あたりの単位時間の保存量の変化(左辺)が、その領域に周辺から単位時間に流入する量と流出量の差(右辺第一項)と、その領域内で発生する量(右辺第二項)の和であるという意味である。
最初に運動量を見る。ρを注目する領域の単位体積中の質量(濃度)、vをその運動速度(流速)とすると、保存量Yは、ρv(濃度×流速)のベクトルで表される。そして、Jはρvとvのテンソル積と、それから圧力テンソルρPを引いたテンソルで表される。そして働く外力は、重力ρG(ベクトル)だけとすると、保存式(運動方程式)は
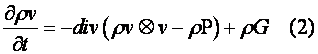
と書かれる。
次に、エネルギーについて見ると、保存量は、運動エネルギーρv2/2と内部エネルギーρuの和となるが、uは顕熱比熱と温度を用いて、CaT、と表す。Jは対流熱ρCaTvと伝導熱kgrad Tの和となる。そしてφは、単位体積単位時間当たりの相変化や化学反応の生成質量で、その単位質量あたりの潜熱(反応熱)をqとして、エネルギー保存式は、
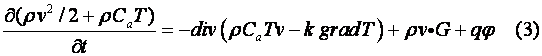
と書かれる。
次に、質量保存式であるが、それは、注目する領域で起こる相変化や化学反応に対応して建てられ、関連する物質ごとに、添え字iをつける。このとき、そのi生成物の保存量はρiである。そして、Jiはρivi(対流)とDigradρi(拡散)の和となる。Diは拡散係数、である。これらを用い、質量保存式は、一般に
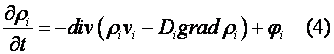
と書かれる。
例として、Al-Cu-Si合金の凝固過程に適用しよう。溶湯が鋳型に注がれて、凝固温度に達する前は、φi=φ=0であるから、(2)〜(4)式はφが消え、ρがTやpの関数(状態方程式)として与えられれば、その解は全体の密度ρ、圧力p、速度v(ベクトル)、温度(T)を決める(通常の流体力学方程式)。
凝固温度に達すると、Al-Cu-Si(liquid)→Al-Cu-Si(solid)なる化学(相変化)反応で固相が現れるから、φi=φsiと書く。φsiは、温度や濃度の既知関数として、反応速度論などから別に与えられねばならず、後述する。凝固が始まった領域では、固相の密度ρsと液相の密度ρlを取り上げる。ただしここで密度というのは、固液共存域の単位体積中に存在する固相と液相とガスの質量のことで、ρs+ρl+ρg=ρである。が、簡単のため、本稿ではガスを考えないことにして、ρは一定とする(非圧縮性流体)。このとき、質量保存式はAl-Cu-Si(liquid)→Al-Cu-Si(solid)なる化学反応の全成分について建てられ、固相については、(4)式の添え字をiからsに代えた(5)式、固液両相を加えた全体について(4)式の添え字を取り、左辺を0とした(6)式が成立する。
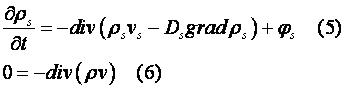
なお、できた固体が非常に小さいと,ブラウン運動による固体の拡散が起こり、溶湯中で結晶核となる。これが(5)式右辺の拡散項Dsgradρsに相当する。この固体は、ある程度大きくなるまで、溶湯と同じ速度vs=vとなるが、表面張力の関係で、やがて型壁から続く固相に付着する。
つぎに、運動量保存式を見る。固体が静止した固相に付着していればvs=0。液体中に浮遊していれば、時に、vs≠vで、重力偏析などを起こすが、これを無視すれば、vs=vとすることができる。更に、溶湯の流れは、鋳込み時の乱れが粘性によって時間と共に納まる過程を経るが、計算を簡略化して、粘性を無視すれば、(2)式は完全流体の式、

となる。圧延用インゴットなど、大きな鋳物で、マクロ偏析やマクロ組織を問題とするときは、(7)式を使ってvを求めること(自然対流計算)も有効かも知れない。中小形鋳物では、(7)式では乱れの急速な減衰を計算することは出来ない。(7)式もあきらめて、vとして適当な値をとることとなる。ダイカストの場合は、vのおよその値が、プランジャー速度と鋳型形状から知られるので、この値を(7)式へ代入して圧力分布を逆算することも可能かも知れない。いずれにしても、複雑な(2)式を直接計算することは避けたい。
次に、エネルギー保存式(3)は、ρが一定のとき、次のように変形され、温度変化を与える。
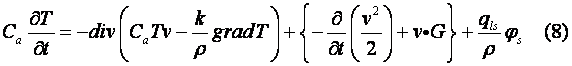 右辺第1項は対流と伝導の熱、第2項は運動とポテンシャルエネルギー、第3項は凝固潜熱を表す。これらは、上に見たごとく、鋳物の種類に応じてvを与え、適宜簡略化することが出来る。右辺第2項は、重力鋳造では第3項に較べて小さいが、ダイカストの場合は金型内で急速に速度が失われるので、無視できない大きさとなる、
右辺第1項は対流と伝導の熱、第2項は運動とポテンシャルエネルギー、第3項は凝固潜熱を表す。これらは、上に見たごとく、鋳物の種類に応じてvを与え、適宜簡略化することが出来る。右辺第2項は、重力鋳造では第3項に較べて小さいが、ダイカストの場合は金型内で急速に速度が失われるので、無視できない大きさとなる、
以上(5)〜(8)式に凝固速度φs=φs(T)(後述)を加えて、解くことによって、密度ρs、圧力p、速度v(ベクトル)、温度(T)が求められる。
次に、Cu(in liquid)→ Cu(in solid)の反応について、質量保存式を建てよう。状態図によると生成物質はα相であるからCu(in melt)→ Cu(in α)と書いてもよい。この質量保存式は、液相と固相に対して、(4)式を適用して、
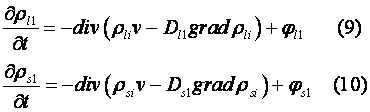
と書かれる。ここで添え字lが液相、sが固相、1がCuを表す。
また、シリコンに関する反応、Si(in liquid)→Si (solid)についても、Siを成分2とし、Si相が単独成分であることを考慮して、つぎの(11)、(12)式が建てられる。
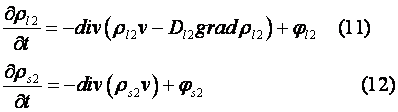
(9)〜(12)式の反応速度には、その定義から、φs1=−φi1=φ1、φs2=−φi2=φ2の関係があり、φ1とφ2にAlの凝固速度を加えたものが、(8)式で示したφlSであろう。これらは何れも温度と濃度の関数である。その関数が決まると(5)〜(12)式の解として、v、T、p、ρs、ρl1、ρs1、ρl2、ρs2、が定まることになる。これによって、金属組織の形成機構が分かるであろう。このφの関数形は状態図と反応速度論を使って組み立てられる筈であるが、未完成である。また、本稿は予定頁数にも達したので、ここで筆を置く。
3.今後のこと
筆者(77歳)は、もう少し早く本稿で述べた段階に達していれば、鋳造にもっと貢献できたように思える。他用にまぎれて今日まで遅れ、大した役に立たなかったことをお詫びする。この後、本稿の読者の中から意欲ある人が出て、この仕事を進めてくださるよう、お願いする。
参考文献;
1)梅村晃由:鋳物の凝固の関する熱および物質移動論的研究、東京大学学位論文
(1978)