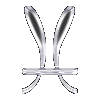第五夜 アフロディーテ  「フロントにお花が届いておりますので、これからお届けにあがってもよろしいでしょうか。」 三時の茶を飲みながら離れで寛いでいると美穂から電話が来た。 「俺達に花が届いているそうだ。 今、持って来てくれる。」 「ほぅ、誰からだろう?」 碁盤を前にして茶をすすったカミュがパチリと石を置く。 定石の本を片手にさっきから研究に余念がないのだ。 最近インターネット碁というのを始めたカミュはネット上での対戦が長引いて夜の時間にくい込んだこともあり俺をやきもきさせる。 先週などは、夕食後にほんのちょっとだけと言ってネットを開いたカミュが以前対戦したことのある手頃な相手を見つけ、「すぐ終らせるから」 と言って始めた試合が3時間半にもなり、フトンの中で今か今かと待っていた俺をげんなりさせた。 「おい、まだ終らないのか?」 待ちくたびれて様子を見に行くと、俺にはさっぱりわからない白と黒の丸い模様が盤面を埋め、画面に向ってきっちりと正座したカミュは次の一手を探りながら長考しているらしい。 「そこまで局面が進んだら、先を読んで負けを認めたほうが投了するもんじゃないのか? 勝てない勝負にしがみつくのはみっともないぜ。」 「横から余計な口出しはしないでもらいたい。 三十手先までは読んでいる。 むろんそこで私が勝つ。」 ちっ………そんなに待たせるなよ………長考しながら双方合わせて六十手打ったら、いったいどれだけかかるんだ? いい加減に切り上げてもらわないと、こっちの身がもたん! 「まあいいさ、俺は俺のやり方でやらせてもらう。 時間を守らなかったのはお前のほうだからな。」 「お前のやり方とは………あっ…」 カミュが自分の石を画面上に一つ置いたのをみすましてから、後ろからやんわりと抱き締めて首筋に口付ける。 「よ、よせっ!」 「やだ!よさない! こんなに待っていたんだから、辛抱強いギャラリーにもご褒美があって当然だろう♪」 「でもまだ対戦中で………あ……ミロ…」 カミュの耳朶はほんとうにやわらかいのだ。 「大丈夫だよ………さっきからお互いに3分は長考してるじゃないか。どうせどこの誰ともわからない相手だし、俺がお前になにをしていたって見えやしない。 3分あれば………ほら…充分だ………」 「でも……あの………こんなことでは考えが……まとまらなくて…次の………石が……」 「だから急に調子を崩して負ければいいんだよ、よくある話じゃないか。 一手打ち間違えれば、あっというまに局面は向こうに有利になる。 そしたらすぐに投了だ。」 「ミ……ロ……そんな……」 結局カミュは三手打ったところで投了し、その日のネット碁は終わりになった。 もちろん俺のほうは投了する気はさらさらなかったので、持ち時間を十二分に使って有意義な夜を過ごしたのだった。 そんなことを思い出して俺がほくそ笑んでいると玄関の呼び鈴が鳴った。 「お花をお持ちいたしました。」 「えっ、こんなに?」 応対に出た俺もさすがに驚いた。 切り花が入っているらしい長方形の長い箱が四つある。 美穂だけでは手が足りなくてもう一人のスタッフと一緒に運んできたのだ。 「数が多いので、大きな花瓶もあとからお持ちいたします。」 そのときにはカミュも出てきて眼を丸くした。 「アフロからだぜ、どうやらバラをくれたらしい。」 箱にはギリシャ語で生花と書いてあり、奥に運んであけてみるとそれはそれは見事な蒼薔薇がたくさん詰まっている。 「ほぅ! なんと見事な!」 「さすがだな、ここまで色を鮮やかに出すのは並大抵じゃないぜ!」 アフロの腕前に感心していると美穂が大きな花瓶を届けにきた。 「ああ、ありがとう、あとはこっちでやるから。」 一箱に50本、全部で200本の薔薇は実に壮観だ。 「こんなに切ってしまって双魚宮の分はあるのだろうか?」 「大丈夫だよ、それに約束だったし。」 「約束とは?」 「ええと………うまく咲いたら届けてくれるって約束をしたことがあるんだよ、だいぶ前に。」 きちんと200本の蒼薔薇を届けてくれたことに感謝せずにはいられない。 今夜が楽しみというものではないか。 そして俺の予想通りの効果だったのは言うまでもない。 丁寧に花びらをとってカミュの上から散らすと白い肌と蒼い花びらとの対比が実に美しくて俺の心を躍らせた。 高雅な香りがカミュを酔わせ、甘い吐息は夜を染める。 さすがにアフロの薔薇だ………最高の夜だぜ♪ 俺達は心ゆくまで蒼い夜を楽しんだ。 一週間後のことだ。 離れに一通のファックスが届けられた。 「アフロディーテが日本に来るそうだ。 バラの世話が一段落したので時間ができたらしい。 ここに泊まってもらってもよいか?」 「ああ、かまわないさ。 蒼薔薇では世話になった。 今度は俺たちがお返しをするべきだろう。」 すでにデスマスク、サガ、老師が泊まっているのだ。 小さいころから親身になって世話をしてくれた双魚宮の聖闘士を歓待するのは当たり前だろうと俺は考えた。 そのときはカミュを抱けなくなるが、そのちょっとした禁欲期間がそのあとの興趣を増すと思えばそう悪いものでもないのだった。 アフロの滞在がいつまでになるかわからないので、その夜は俺だけでなくカミュもかなり積極的だった。 至極いい雰囲気で朝までカミュをいつくしんだのだ。 「少し寒いな……」 気がつくとカミュの白い背が半分ほど見えている。毛布を手繰り寄せてそっと首元まで包んでやった。 外はもう明るくて鳥の声が聞こえるのもいつものことだ。 「ん………」 まだ覚めきらない声が甘く響く。 「まだ起きるには早すぎる。 もう少し楽しみたいね。」 そう言って引き寄せると心なしか身体が熱っぽい。 「ん? もしかして熱でもあるのか?」 「いや、そんなはずは…」 「ちょっと気になるな。 最近あちこちではしかが流行ってるっていうし、気をつけたほうがいいぜ、あとで美穂から体温計を借りてこよう。」 「そんな大袈裟な……」 「それは俺だって、俺があんまり可愛がりすぎたせいでまだ熱が冷めないの?とか気楽に言いたいところだが、俺がインフルエンザになったことを思うと冗談ばかり言っていられないからな。」 「ばかなことを…」 たとえ熱があるにしても、頬を染めてうつむくカミュがなんともいえず可愛くて俺はやさしく口付けていった。 「37.1度だ。 お前にしては高いほうだろう。」 「うむ、やや高い。」 「アフロが来るが大丈夫かな?」 「支障はあるまい。 だいいち、熱が37.1度だからといって来客を断るわけにはいかぬ。」 「まったくだ。」 こうして昼過ぎにアフロディーテがやってきた。 それもただの来訪ではない。 「まぁ〜っ、こんなにたくさん!」 美穂が驚くのも道理だ。 アフロは自分の初めての日本での休日を美しく彩ろうと考えたらしく、切れるだけのバラを切ってクール便で持ち込んできたのだ。 「このたびはお世話になります。 趣味で育てたバラですので、どうぞこちらでも飾ってお使いください。」 にっこり笑いながら宿泊者名簿にペンを走らせるアフロは笑顔を振りまき、いっぺんで宿のスタッフを虜にしたようだ。 趣味で育てたというのは本当だが、プロの園芸家をはるかに凌ぐ色とりどりのシークレットラブやハネムーンやブライダルピンクがロビーにあふれ、たしかに贅沢極まりない。 宿の主人がアフロと相談しながら、装飾用、薔薇風呂用、離れ用とバラを選り分けてさっそくあちこちに飾り始めた。 「さあ、バラのことも済んだので君達と積る話でもしようか。」 「ああ、日本のことにはずいぶん詳しくなったぜ。 聖域には変わったことはないか?」 アフロを離れに案内しながらちらっとカミュを見ると、若干頬が赤いが足取りはしっかりしており、とくに何ということもないようだ。 庭の植栽に目をやって興味深そうにしているアフロに気付かれないように 「気分はどうだ?」 とささやくと 「たいしたことはない。」 といつも通りの返事が返ってきた。 「デスマスクから話は聞いている。 日本食とか温泉とか、なかなかユニークじゃないか。」 離れの座敷を見回して畳や座布団に目を留めたアフロディーテが説明を求めるのでさっそくカミュが由来だの特徴だのを話し始めた。 落ち着いた話しぶりは普段と変わることがなくて、どうやら熱も下がったとみえる。 「もう薔薇風呂の用意ができた頃だが、入りに行くか?」 「ああ、楽しみだね。 双魚宮ではいつもやっているが、オリエンタルなアレンジではどうなるのか興味がある。」 「カミュは人と入るのが苦手なんでね、俺が付き合うよ。」 「そうらしいね、それもデスから聞いている。」 デスは俺達のことにはどのくらい気付いているのだろう。 先日ここにやってきたときにはそんなことは仄めかしもしなかったが、考えてみればカミュが心理攻撃を受けて変調をきたしたときに俺とカミュの抱擁を目撃しているのだから、デスは俺達のつき合いについては確信を持っているのに違いない。 そもそもカミュがシベリアにいたときからなにかといえば俺に助言、といえば聞こえはいいが、面白がってちょっかいを出してくれたからな。 まあ、知っていると考えたほうがいいだろう。 アフロにはなにも見せたことはないし、むろん仄めかされたことなど一度もないが、 デスとアフロはかなり親しいからな…………アフロも知っていると考えたほうがいいかもしれん 「ところで蒼薔薇はどうだったかな?」 浴衣とバスタオルを揃えていたカミュの肩がピクリとした。 「ああ、とても素晴らしかったぜ! 日本のサントリーが2004年に青薔薇を開発して世界をあっと言わせているが、双魚宮のバラはそれをはるかに上回る素晴らしさだと断言できる! マスコミに知れたら押し寄せて来るだろうな。」 「私が巷間のばら愛好家ならそれもいいだろうが、あいにく俗世間とは一線を画している聖域の最上宮に咲く薔薇だ。君達に愛でてもらうだけで充分だよ。」 アフロの突然の蒼薔薇発言に、白い肌に散らせた蒼い花びらの美しさがまざまざと脳裏によみがえる。 いや、この場合は蒼い花びらを散らせた白い肌の美しさ、と表現したほうが正しいかもしれん。 ともかく心がそっち方面に向うのを必死で押さえ込みながらアフロの関心をもっとアカデミックなほうに向けると、青色色素デルフィニジンの話やら、英語でブルーローズといえば 『 不可能、有り得ないこと 』 の代名詞だとかの極めて穏当な話になってほっとした。 もしかしてカミュの心拍数が上がったことを察知したアフロが気を利かせて話題を変えてくれたのかもしれないが、今は気にしないことにする。 予約しておいた家族風呂に行くと、ゆらゆらと立ち昇る湯気に様々な色の薔薇の花が揺れていかにも美しい。 「ほぅ、これはこれは!」 「この宿では週に一回はこうして花風呂をやるのだが、なんといっても薔薇の人気が一番高いそうだ。」 アフロはデスから話を聞いていたこともあるのだろうが、裸になるのが苦ではないらしく、脱衣所でさっさと裸になるとさっそく硝子戸を開けて目の前に展開する自分の薔薇を見て悦に入っている。 日本での湯の入り方を教えると、「なるほど、それは合理的だ!」 と感心しながら身体を洗い、湯に浸かってさっそく薔薇の様子をしげしげと観察し始めた。 「双魚宮の浴槽はさほど大きくないので使う花数も50輪がいいところだが、これほど大きい浴槽だと200輪は浮かべられるね、たいそう結構だ。木製の浴槽も初めてだが肌当たりが実にいい!」 「おかげで素晴らしい風呂が楽しめる。 贅沢だよ。」 カミュと入れないのは残念だが、アフロが滞在している限りそれは有り得ない。 あとで一人で内風呂に入って薔薇風呂を楽しんでもらうしかないだろう。 そのあと、菖蒲湯やゆず湯の話をするとアフロはずいぶんと面白がった。 「すると日本では5月5日に菖蒲湯、12月の冬至にはゆず湯に入るのが全国民の習慣になっているのか? これは面白い!」 「ああ、そうだ。 その時期になると野菜売り場では必ず菖蒲と柚子を売る。 どこの宿泊施設でもその日は必ずその湯を用意するって話だ。」 「すると君達も去年の12月にゆず湯に入ったのだから風邪を引かないというわけか。」 そう言われて、去年の11月にインフルエンザにかかったことを思い出したのは事実だ。 でも、あれは特別だ なにしろインフルエンザだからな、風邪とは違う それにゆず湯に入って11ヶ月も経っていれば効目が切れても仕方ないだろう 「俺たちは風邪とは無縁だな。 温泉のおかげで極めて健康だ。 今夜の食事も美味いと思うぜ。」 「それは楽しみだ。」 ピンクの薔薇を手に取ったアフロがうっとりと香りを吸い込んだ。 そしてその夜の食事には特別に春野菜のサラダが付け加えられ、エディブルフラワーとしてアフロの薔薇の花びらが皿の周りを飾っていた。 「ああ、きれいだ!」 「私の薔薇には農薬は一切使ってないからね。 それにバラの花弁には食物繊維とビタミンCが豊富に含まれていて身体にも良い。」 サラダを供されたほかの客にも好評なのが美穂の口から伝えられ、アフロの機嫌もいい。 「ビタミンCは風邪にもいいって言うからな、肌の調子もよくなったりして!」 「ますます結構だね♪」 カミュが口数の少ないのがちょっと気になったが、いつものことだろうと考えた俺はとくに気にもしなかった。 アフロのフトンが奥の十畳間で、俺たちのフトンが手前の八畳間に敷いてあるのは老師が来たときと同じだ。 「今日は楽しかった。 お休み。」 アフロが境の襖を閉め、俺達も横になる。 といってもむろん何をするわけでもなく静かに眠るだけなのだが、ほんの少しくらいはいいだろうと考えた俺はアフロの気配を慎重に探りながら、きちんと仰向けになって眼を閉じているカミュにそっと唇を寄せた。 軽く触れ合わせてゆくと驚いたように眼を開けたカミュが眉をひそめて顔をそむけてしまう。 俺は笑って額を軽くつつくと自分のフトンにもぐりこんだ。 思ったより熱い唇が心に残った。 翌朝の朝食でカミュが早々に箸を置いた。 「あれ? もう終わりか?」 「うむ……あまり食欲がない。」 「大丈夫か?」 「どこか具合でも?」 俺とアフロが心配してもカミュは取り合わずにいるが、そういえばちょっと首筋が赤くないだろうか? 「戻ったら熱を測るからな。」 「熱などないが。」 「なければないで、確認だけはさせてもらう。」 そして実際に熱はなかった。 「36.6度だ。 納得したか?」 「ああ、わかったよ。 たしかに平熱だ。」 その日は牧場に行って過ごし、少しは乗馬経験のあるアフロと周回コースを何度も回って楽しんだ。俺とカミュが競っているのをアフロはにこにこ笑いながらゆっくりとついて来る。 時々は輪乗りをしてアフロが追いついてくるのを待ちながら、久しぶりの乗馬を俺たちも楽しんだ。 そしてその次の朝だ。 鳥の声で目覚めた俺はアフロを誘って露天風呂に行った。 ゆっくりと朝焼けの空を楽しんで離れに戻ってくると、カミュがまだ寝ている。 いつもならとっくに起きて身仕舞いを整え、茶を淹れる用意をしてる筈なのに珍しいこともあるものだ。 「おい、もう起きないか? 茶を飲もう。」 声を掛けながらフトンをざっと畳み始めたが返事もないのだ。 「カミュ?」 肩を軽く叩いて向こうを向いている顔をのぞきこんだ俺は目をみはった。 眉を寄せた顔は赤くていかにもつらそうだ。 慌てて額に手を当てると燃えるように熱い。 「おいっ、どうした? 熱があるじゃないか!」 俺の声に驚いたアフロが寄ってきてカミュを仰向けにした。 眼を開けるのも億劫そうなカミュは荒く息をつくのみで返事もしない。 「体温計を!」 アフロに催促されて、幸い借りっぱなしだった体温計を持ってきて脇に挟み込む。 「41.3度だ。」 「解熱剤をもらってくる!」 俺は急ぎ足でフロントに向った。 「インフルエンザですね、ごらんの通りC型です。」 美穂の勧めで医師の往診を受けることになり、簡単な試薬で判定してもらった結果はインフルエンザだった。 「だってカミュは予防接種を受けたのに!」 俺がぼやくと、 「予防接種はあらかじめ流行る型を予想して作られたワクチンだそうですから、他の型にかかることもあるんだそうですの。」 気の毒そうに美穂が言い、そう聞かされてはどうしようもないのだ。 あのときに予防接種を受けなかった俺がかかったのは仕方がないが、流行の型ではなかったために予防接種を受けていたカミュがかかってしまったのは、よほどに運が悪いのだろう。 「せっかく来てもらったのに、こんなことになって落ち着かなくてすまない。」 「なに、気にすることはない。 小さいときからいろいろと面倒を見てきたのだし、気にしなくていいからね。」 アフロはそう言ってくれるが、カミュが臥せっているのでは何処に出かけようもないのだ。 俺たちが留守にしたらカミュのちょっとした世話を美穂に頼まねばならず、それはカミュの望むところではないし、美穂の仕事の妨げにもなる。 アフロが席をはずしているときにそっとカミュに聞いてみた。 「はら、例の…鼠径クーリング………したほうがいいか? そのほうが熱が早く下がるんだろ?」 力なく眼を開けたカミュが、ただでさえ赤い頬の色をさらに濃くしたようだ。 「いや………アフロもいることだし、遠慮する………心配をかけてすまない…」 「それにしてもなかなか熱が下がらない。……つらくないか?」 手を握るとかなり熱っぽくて、握り返す力もないのか俺に手を預けたままなのだ。 「つらいといえばつらいが、今までよりはましだ………」 「え? 今までって?」 意味がわからなかった俺が尋ねると、カミュが困ったように眼をそらす。 「今ならアフロもいないし、なんでも言っていいんだぜ。」 「あの………アフロの来た朝からだんだん熱が上がったのが自分でもわかって……それを無理に抑え込んでいた。」 「なにっ?」 「予防接種はしてあったし、普通の風邪なら問題ないと思っていたが、あいにくインフルエンザで、こんなに熱が高くなって……」 「………もしかしてお前……俺が無理矢理に鼠径クーリングをすると思ってた?」 「ん………あの…」 カミュが真っ赤になってフトンを引き寄せた。 俺は盛大に溜め息をつく。 「あのなぁ………お前が作った氷ならずっと融けないだろうが、ここの冷蔵庫の氷ではすぐ融ける。 アフロがすぐ側にいるのに、お前の浴衣の裾をめくって何度も鼠径クーリングを取り替える勇気は俺にはないぜ!かえってお前の熱が上がる!具合が悪いと思ったら、ごまかしてないで最初から言えよ! 無理して乗馬まで付き合うから症状が悪化したんじゃないのか?!」 「すまない……」 それきり眼を閉じたカミュが黙り込み、俺としても少々言い過ぎたかなと気がもめる。 「ちょっと言い過ぎた………すまん………そろそろ次の解熱剤を飲んだほうがいいだろう。」 「ああ、そうだな……」 せめてもの償いに熱い身体をそっと抱き起こして口移しで飲ませると、ちょっと苦い味がした。 「私はかまわないけど、仲が良すぎるのではないかな?君も41.3度だ。」 アフロの言うのももっともだ。 翌朝から俺も熱を出し、医師の往診を受ける破目になった。 やっぱり薬の口移しがよくなかったらしい。 「やはりC型ですね、安静にして消化の良いものを食べるように心がけてください。」 医師が帰ってゆき、離れの玄関先でアフロと美穂が頭をさげてくれたようだ。 「それにしてもここまで顕著にうつるとは思わなかった。 この上は私にうつらないことを祈らせてもらおう。」 「ほんとにすまん………」 「まあいいさ、これも経験だ。インフルエンザなんてお医者様でも草津の湯でも治るのだから、君達のかかる病としては軽い部類だね。」 そう言ったアフロが美穂と一緒に薬局に薬を取りに行くため玄関を出て行った。 ………え? アフロは今なんて言った? お医者様でも草津の湯でも………って、それって……… 恋の病は直りゃせぬ、という有名な文句が浮かんできて かっと身体が熱くなる。 幸いなことに、眼を閉じているカミュに聞こえた気配はなさそうだ。 やっぱ、バレバレだぜ……… そういうことなら、とっくにうつってるんだし、アフロのいないうちにもう一度…… 開き直った俺は薔薇にあふれた病間で眠るカミュに唇を重ねていった。 ああ、また熱が上がる。 久しぶりの十二夜です。 五月とくれば、やはりアフロの出番でしょう! ミロ様も病人なんだからおとなしくしていてくださいね ← もはや無理です……… 薔薇風呂の話は ⇒ こちら (古典読本 「薄朱けの」 ) 青薔薇の話は ⇒ こちら インフルエンザの話 ⇒ こちら ( 東方見聞録 「インフルエンザ」 ※ サントリーの青いバラ ⇒ こちら |